
フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法
介護にまつわるお役立ちコラム

高齢になると多くの方が経験する足のむくみ。「いつものこと」と見過ごしがちですが、実はその症状、体が発する大切なサインかもしれません。
この記事では、なぜ高齢になると足がむくみやすくなるのか、その原因を詳しく解説します。さらに、危険な病気のサインを見分けるポイントから、今日からご自宅で実践できる優しい解消法までご紹介しますので、ぜひご自身の体をいたわるヒントにしてください。

高齢になると足がむくみやすくなるため、「年齢のせいだから」と諦めてしまう方は少なくありません。しかし、そのむくみは単なる老化現象ではなく、重大な病気が隠れているサインの可能性もあるため注意が必要です。
そもそも「むくみ(浮腫)」とは、血液中の水分が血管の外に染み出し、皮膚の下に余分に溜まってしまった状態を指します。これを放置してしまうと、足が動かしにくくなって歩行が不安定になり、転倒のリスクが高まります。さらに、背景に心臓や腎臓の病気が隠れている場合、治療が遅れて症状が重症化してしまう危険性もあるのです。
参考:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター|足の腫れ・むくみの原因は?

高齢者の足のむくみは、ひとつの原因だけでなく、体の変化や日々の習慣といった複数の要因が絡み合って起こることが少なくありません。原因を正しく知ることが、ご自身に合った適切なケアや、必要な場合の医療機関への受診につながります。
年齢を重ねると体にはさまざまな変化が現れ、それが足のむくみの大きな原因となります。
まず挙げられるのは、ふくらはぎの筋力低下です。ふくらはぎの筋肉は、足に戻ってきた血液を心臓へ押し上げる「ポンプ」の役割を担っています。しかし、加齢により筋肉量が減少すると、このポンプ機能が弱まり、血液が足に滞りやすくなります。
次に、血管の老化です。年齢とともに血管は弾力を失い硬くなるため、血流がスムーズに流れにくくなります。さらに、全身に血液を送り出す心臓のポンプ機能も低下することで、血行不良が進み、むくみを生じやすくなります。
日々の何気ない生活習慣も、足のむくみに深く関わっています。
例えば、塩分を多く含む食事は体に水分をため込みやすくし、むくみを引き起こします。加えて、長時間同じ姿勢で過ごしたり、運動不足が続いたりすると、ふくらはぎの筋肉が十分に働かず、血流が滞りやすくなります。
一見良い対策のように思える「水分を控えること」も逆効果となる場合があります。体が水分不足を感じると、かえって水分をため込もうとする防御反応が働き、むくみを悪化させてしまうため、適度に水分を補給しましょう。

ほとんどのむくみは生活習慣の見直しで改善が期待できますが、中には病気のサインとして現れる危険なむくみもあります。特に、以下のような症状が見られる場合は、自己判断せずに必ず医療機関を受診してください。
片足だけが異常にむくむ
急にむくみがひどくなった
足のむくみに加えて、息切れ、動悸、体重の急増や尿の異常といった他の症状がある
これらのサインを見逃さず、早期に適切な治療を受けることが非常に重要です。
両足が同じようにむくむ場合、心臓や腎臓など、全身に関わる病気の可能性があります。
心不全:心臓のポンプ機能が低下し、全身の血流が滞ることでむくみが生じます。特に夕方にむくみがひどくなり、息切れや動悸を伴うことがあります。
腎不全:腎臓の機能が低下し、体内の余分な水分や塩分を尿として排出できなくなることでむくみます。特に朝、顔やまぶたが腫れぼったくなるのが特徴です。
肝硬変:肝臓の機能が低下すると、血液中の水分を保つ役割のタンパク質が減少し、むくみの原因となります。お腹に水が溜まる(腹水)こともあります。
甲状腺機能低下症:体の新陳代謝を促す甲状腺ホルモンの分泌が減ることで、全身の代謝が落ちてむくみやすくなります。
片方の足だけにむくみが出る場合は、その足自体の血管やリンパ管に問題が起きている可能性があります。
深部静脈血栓症(エコノノミークラス症候群):足の深い部分にある静脈に血栓(血の塊)ができ、血流がせき止められてむくみや痛みが起こります。この血栓が肺に飛ぶと命に関わる「肺塞栓症」を引き起こす危険な病気です。
下肢静脈瘤:足の静脈にある、血液の逆流を防ぐための弁が壊れ、血液が足に逆流して溜まることで血管がこぶのように浮き出て見えます。むくみやだるさも引き起こします。
リンパ浮腫:がんの手術でリンパ節を切除したり、放射線治療を受けたりした後に、リンパの流れが滞ってむくみが生じることがあります。

病気が原因ではないむくみは、マッサージや運動、食事などの日々のセルフケアで改善・予防が可能です。大切なのは、毎日少しずつでも継続することです。無理をせず、自分のペースでできることから取り入れていきましょう。
自宅で血行を良くするには、優しいマッサージや簡単な運動を取り入れるのがおすすめです。
マッサージは、足先から心臓に向かってふくらはぎをやさしくさすったり、足首をゆっくり大きく回したりします。強く揉んで痛みを感じるほどになると逆効果なので、「気持ちいい」と思える程度にとどめましょう。
運動では、椅子に座ったままできる「かかと上げ」や「足首の曲げ伸ばし」が手軽です。「かかと上げ」では、つま先を床につけたまま両かかとをゆっくり持ち上げ、数秒止めてから静かに下ろします。「足首の曲げ伸ばし」は、つま先を手前に引いたり遠くに伸ばしたりするだけの簡単な運動です。ふくらはぎの筋肉を意識して、ゆっくり大きく動かしましょう。
食事で意識したいポイントは、「減塩」「カリウムの摂取」「適切な水分補給」の3つです。
お味噌汁や漬物など塩分の多い食事は、食べ過ぎないように心がけましょう。だしの旨味や香辛料を活用して味を整えると、塩が少なくても物足りなさを感じにくくなります。さらに、余分な塩分を排出してくれるカリウムを豊富に含む食品(バナナ・ほうれん草・ひじきなど)を積極的に取り入れることも大切です。
なお、むくみを気にして水分を控えるのは逆効果です。喉が渇く前に、こまめに水分を補給するようにしましょう。
むくみは、日常のちょっとした工夫でも和らげることができます。
例えば、横になるときや座っているときにクッションや座布団を足の下に置き、足を心臓より少し高い位置に保つと、足にたまった血液が戻りやすくなります。さらに、血行を妨げないよう、体を締め付けないゆったりとした服装や靴下を選ぶことも効果的です。加えて、立ち仕事やデスクワークが多い方は、足に適度な圧力をかけて血流を促進する「弾性ストッキング」を活用すると、むくみの予防や改善に役立ちます。

セルフケアを続けてもむくみが改善しない、一人で運動やマッサージを行うのが難しい、という方もいらっしゃるでしょう。そのような場合は、かかりつけ医に相談するとともに、訪問介護・看護といった専門家のサポートを検討するのも一つの方法です。
自費の訪問介護・看護サービス「イチロウ」なら、制度の枠にとらわれない柔軟なサポートが可能です。例えば、「むくみ解消のマッサージを定期的に行ってほしい」「リハビリのための散歩に付き添ってほしい」といった、一人ひとりの細やかなご要望にお応えできます。専門知識を持ったヘルパーが、ご自宅での快適な生活を支えます。

足のむくみで受診を考えたとき、何科に行けばよいか迷うかもしれません。そんなときは、まずご自身の体をよく知っている かかりつけの内科医に相談しましょう。かかりつけ医が診察したうえで、より詳しい検査や専門的な治療が必要だと判断した場合には、循環器内科(心臓)・腎臓内科・血管外科などの専門診療科を紹介してもらえます。
高齢者の足のむくみは、単なる老化現象と片付けずに、その背景にある原因を考えることが大切です。多くは生活習慣の見直しやセルフケアで改善できますが、時には重大な病気のサインである可能性も潜んでいます。
日々のマッサージや運動、減塩を心がけ、それでも改善しない場合や、「片足だけむくむ」「息切れがする」といった危険なサインに気づいたときには、ためらわずに医療機関を受診しましょう。ご自身の体の小さな変化に耳を傾け、健やかな毎日をお過ごしください。
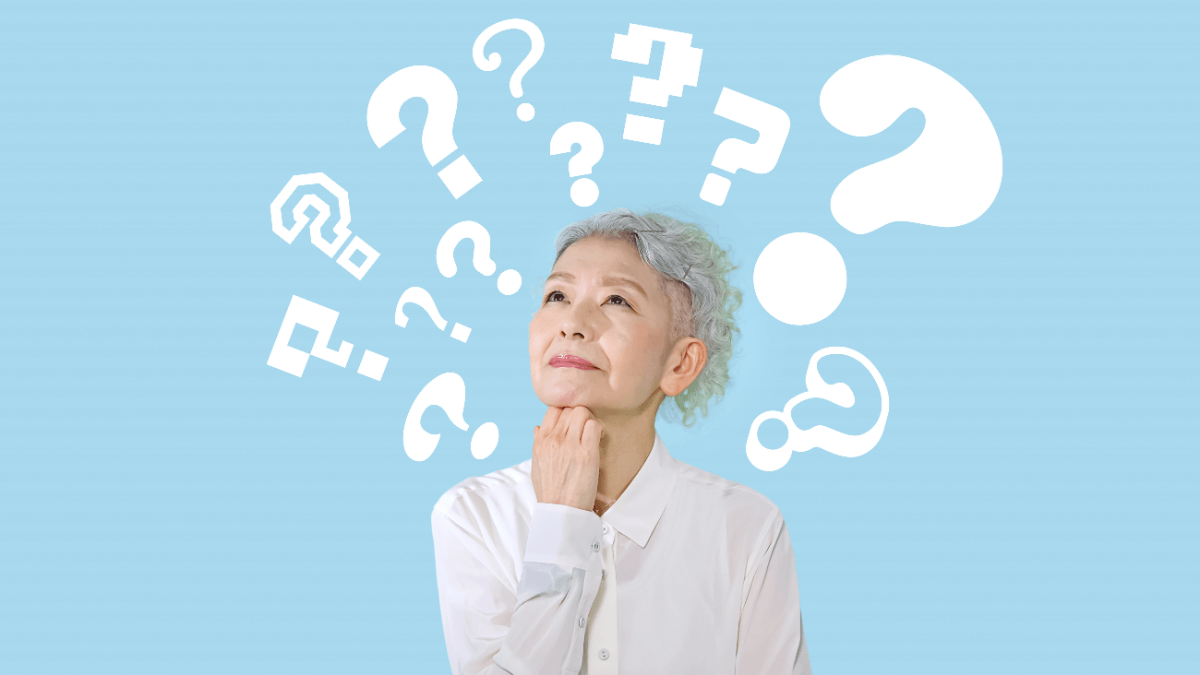
ここでは、高齢者の足のむくみに関するよくある質問とその回答をご紹介します。
慢性的な血行不良によるむくみの場合、基本的には血行を促進する「温める」ケアが効果的です。ぬるめのお湯で足湯をしたり、温かいタオルで足を包んだりすると良いでしょう。ただし、捻挫や打撲などで足が腫れて熱を持っている場合は、炎症を抑えるために「冷やす」のが適切です。
絶対に自己判断で薬の服用を中止しないでください。薬には、病気をコントロールするための重要な役割があります。むくみが気になった場合は、必ずその薬を処方した医師や薬剤師に相談してください。
弾性ストッキングには様々な着圧の強さやサイズがあります。ご自身の足の状態に合わないものを使用すると、かえって血行を悪化させてしまうこともあります。購入する際は、まず医師や看護師に相談し、適切な製品を選ぶようにしましょう。