
フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法
介護にまつわるお役立ちコラム

認知症の方の症状の現れ方は一定ではなく、「昨日できていたことが今日はできない」「時間帯によって言うことが変わる」など、日々の変化に戸惑うご家族は少なくありません。
この記事では、そのような症状の波が特徴的な「まだら認知症」について解説します。まだら認知症の正しい知識を得ることで、ご本人への理解が深まり、ご家族が安心して向き合うための具体的な対応方法がわかります。
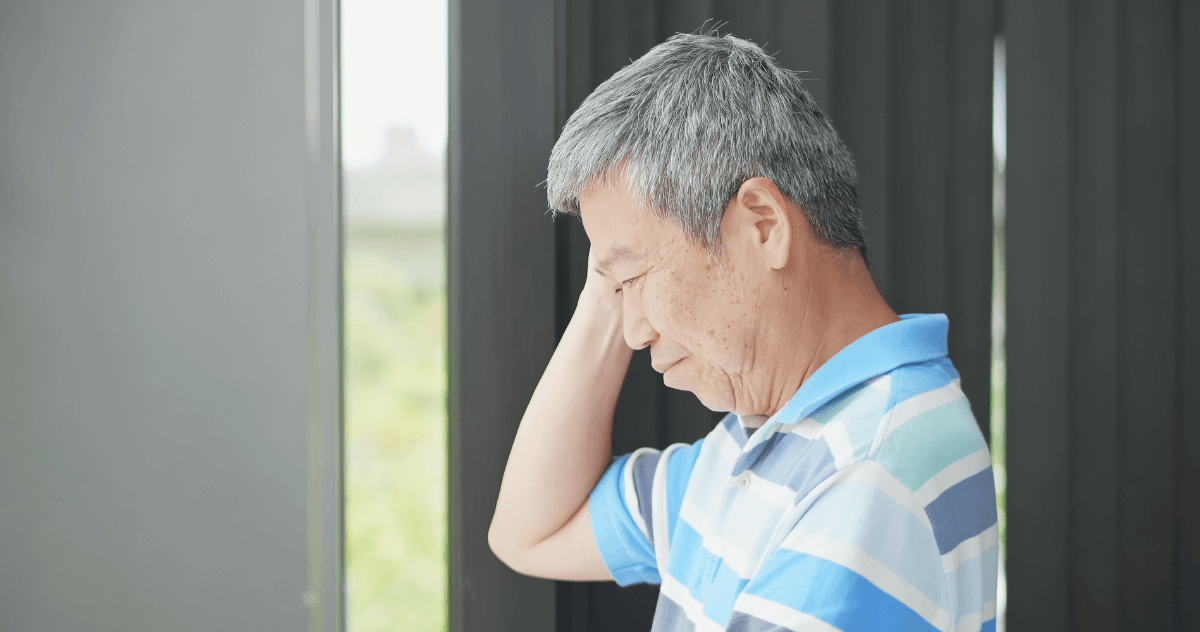
「まだら認知症」とは、特定の病名を指す言葉ではありません。「できること」と「できないこと」の差が激しかったり、日や時間帯によって症状が大きく変動したりする状態を指す言葉です。特に、脳梗塞や脳出血が原因で発症する「脳血管性認知症」の典型的な症状として知られています。
記憶力は落ちているのに判断力はしっかりしている、といった状態が見られるため、周囲からは「怠けている」「わざとやっている」と誤解されやすいのが特徴です。ご本人もできることとできないことのギャップにもどかしさを感じ、ご家族もどう対応してよいかわからず、共に混乱してしまうケースが少なくありません。

まだら認知症の症状にムラや波が生じる背景には、脳の状態や身体的な要因が複雑に関わっています。症状が変動する主な原因は、「脳のダメージの偏り」「脳血流の変化」「その他の身体的不調」の3つです。これらのメカニズムを理解することが、ご本人に適した対応や、症状の悪化を防ぐことにつながります。
まだら認知症の最大の原因は、脳のダメージの偏りです。脳梗塞や脳出血といった脳血管障害によって脳の一部が損傷すると、その部分が担っていた機能は低下します。しかし、損傷していない部分の機能は保たれるため、能力にアンバランスが生じるのです。
例えば、記憶を司る部分がダメージを受ければ記憶力は低下しますが、計算能力を司る部分が無事であれば、複雑な計算は以前と変わらずできる、といった状態が起こります。この能力のまだら状態は、脳血管性認知症の大きな特徴です。
脳の血流量は一日の中でも変動しており、血流が低下するタイミングで一時的に認知症の症状が強く見えることがあります。具体的には、起床直後、食後、入浴後、あるいは体内の水分が不足している時などです。
これは脳血管性認知症に限らず、アルツハイマー型など他の認知症でも広く見られる現象です。特にレビー小体型認知症などでは、自律神経の乱れから食後などに血圧が急降下し、意識がぼんやりしたり、症状が悪化したりするケースもあります。
認知症の方は、便秘、身体の痛み、脱水といった不調をうまく言葉で伝えられないことがあります。その不快感が、興奮しやすくなったり、混乱したりする「せん妄」などの症状として現れるのです。
身体の不調が改善すれば症状も落ち着くため、数日おきに状態の悪化と改善を繰り返すことがあります。この状態が、周囲からは「まだら」な症状の波に見えるのです。症状の変化の裏に、隠れた身体的問題がないか注意深く観察することが大切です。
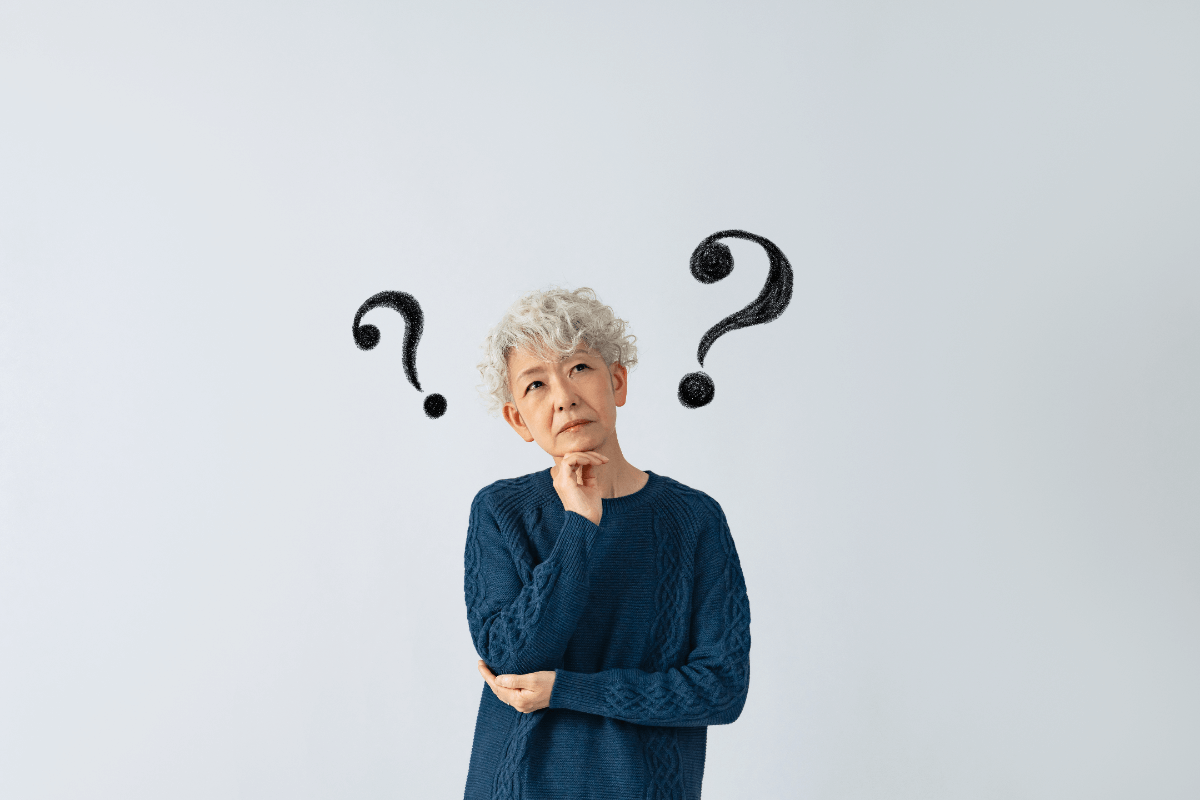
まだら認知症の症状が見られやすい「脳血管性認知症」と、最も患者数が多い「アルツハイマー型認知症」には、いくつかの違いがあります。
まだら認知症とアルツハイマー型認知症の違い
比較項目 | まだら認知症(血管性認知症) | アルツハイマー型認知症 |
本人の自覚 | 理解力などが保たれていることが多く、自身の認知症を自覚している場合が多い。 | 脳全体の機能が低下するため、認知症である自覚がないことが多い。 |
症状の進行 | 脳梗塞や脳出血などを発症するたびに、急に悪化するなど階段状に進行することがある。 | 気づかないうちに発症し、ゆっくりと徐々に進行していく。 |
身体症状 | 歩行障害、手足のしびれ・麻痺、ろれつが回らない、といった身体的な症状を伴うことがある。 | 初期には身体的な症状はほとんど見られない。 |
周辺症状(BPSD) | 認知機能に関する症状が中心で、幻覚や抑うつといった周辺症状は比較的生じにくい。 | 抑うつや不安など、人格に影響を及ぼす周辺症状が現れることがある。 |
このように、「本人の自覚の有無」や「症状の進行の仕方」「身体症状の有無」といった観点から、それぞれの特徴が異なります。これらの違いを知ることが、ご本人への適切な接し方や、今後の見通しを立てる上で役立ちます。
参考:
一般社団法人 日本神経学会|認知症疾患診療ガイドライン2017

まだら認知症の症状の波に、ご家族が振り回されないようにするために、心構えと具体的な対応方法を知っておきましょう。何よりも忘れてはならないのは、「できること」と「できないこと」の狭間で最も苦しんでいるのはご本人であることです。ご本人の尊厳に配慮しながら、「観察と記録」「環境調整」「心の持ち方」の3つのポイントで向き合っていきましょう。
症状がどのようなときに悪化するのかを客観的に記録しましょう。タイミングや状況、きっかけを残しておくことで、変化のパターンを見つけやすくなります。
例えば、「食後に混乱することが多い」「水分をあまり摂らない日は夕方に落ち着きがなくなる」といった記録は、症状の裏にある身体的な要因を発見する手がかりになります。
こうした記録は、医師やケアマネジャーに相談する際の貴重な資料となり、適切な治療やケアプランの作成に役立ちます。ご家族にしか気づけない小さな変化を伝えることが、より質の高いサポートにつながるのです。
症状の波によって混乱やせん妄が起きやすくなるため、特に症状が悪化しやすい時間帯には、ご本人が安全で静かな環境で過ごせるように配慮する必要があります。テレビの音を小さくしたり、照明を明るすぎないように調整したりするだけでも、ご本人の安心につながります。
また、脳血管性認知症では手足の麻痺や歩行障害を伴うことがあるため、手すりの設置や段差の解消といった住環境の整備も大切です。介護保険のサービスを利用すれば、福祉用具のレンタルや住宅改修費用の補助を受けられるため、ケアマネジャーに相談してみましょう。
できる時とできない時があることに、ご家族が一喜一憂してしまうのは自然なことです。しかし、大切なのは「病気には波があるのが当たり前」と捉え、長い目で見守る心構えです。
ご本人の「できないこと」に目を向けすぎず、「できること」を尊重し、自信や尊厳を傷つけないよう配慮しましょう。昨日できなかったことが今日できても、過度に期待しすぎてはいけません。逆に、今日できたことが明日できなくても、責めたりがっかりした態度を見せたりしないが大切です。
症状の波に振り回されないことが、ご本人がマイペースな生活を守る上で最も重要な支えとなります。

ご家族だけで日々の症状の変化を24時間記録し続けるのは、心身ともに大きな負担がかかります。そこで有効なのが、訪問介護サービスなどを利用し、専門家の視点を加えることです。
介護保険外の訪問介護サービス「イチロウ」では、ご家族に代わって食事や排泄の介助、見守りなどを行います。定期的に訪問するヘルパーから「いつ、どのような症状が見られたか」という客観的な報告を受けることで、ご家族だけでは気づけなかった変化のパターンが見えてくることがあります。専門家の視点から得られた的確な情報は、医師への状況説明にも役立ち、より適切な治療やケアへとつながっていきます。
まだら認知症は、ご本人もご家族も混乱しやすい症状ですが、その原因や特徴を正しく理解することで、適切な向き合い方が見えてきます。症状の波は脳のダメージや血流、体調などが影響していることを知り、「波があるのが当たり前」という心構えを持つことが大切です。日々の変化を記録し、安全な環境を整え、時には専門家の力も借りながら、ご本人とご家族が穏やかに過ごせる方法を見つけていきましょう。

ここでは、まだら認知症に関するよくある質問とその回答をご紹介します。
「まだら認知症」は正式な病名ではなく、症状の現れ方を表す通称です。多くの場合、「脳血管性認知症」に見られる特徴的な症状を指して使われます。
一度損傷した脳細胞を元に戻すことは難しく、完治は困難です。しかし、原因となる高血圧や糖尿病などの生活習慣病を治療する薬物療法や、残された機能を維持・向上させるためのリハビリテーションによって、症状の進行を緩やかにしたり、生活の質を改善したりすることは可能です。
ろれつが回らない、手足が動かしにくい、意識がはっきりしないといった症状が急に現れたり悪化したりした場合は、新たな脳梗塞や脳出血を発症している可能性があります。ためらわずに、かかりつけ医に連絡するか、救急車を呼ぶなどの対応を取ってください。