
フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法
介護にまつわるお役立ちコラム

介護保険を利用して福祉用具を購入できることをご存知でしょうか。車椅子や介護ベッドなどの福祉用具は原則レンタルで利用しますが、排泄や入浴に使用する一部の用具については、衛生面の理由から購入が認められています。この記事では、介護保険で購入できる「特定福祉用具」の品目一覧から、2024年4月に新たに導入された選択制の対象品目、購入時の費用負担や申請手続きまで、わかりやすく解説していきます。介護用品の購入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

介護保険制度では、福祉用具の利用について「レンタル(貸与)」を基本原則としています。これは、要介護者の身体状況が時間の経過とともに変化することや、福祉用具自体の機能が向上していくことに対応し、その時々で最も適切な用具を提供できるようにするためです。たとえば、歩行が困難になった方が、リハビリによって改善した場合、使用する福祉用具も段階的に変更していく必要があります。
しかし、すべての福祉用具がレンタルに適しているわけではありません。排泄や入浴の際に肌に直接触れる用具については、他人が使用したものを再利用することに心理的な抵抗感が生じやすく、衛生面でも適切ではないという観点から、「特定福祉用具」として購入の対象となっています。これらの用具は、介護保険を利用して購入費用の一部が給付される仕組みになっており、利用者の経済的負担を軽減しながら、必要な介護環境を整えることができるようになっています。
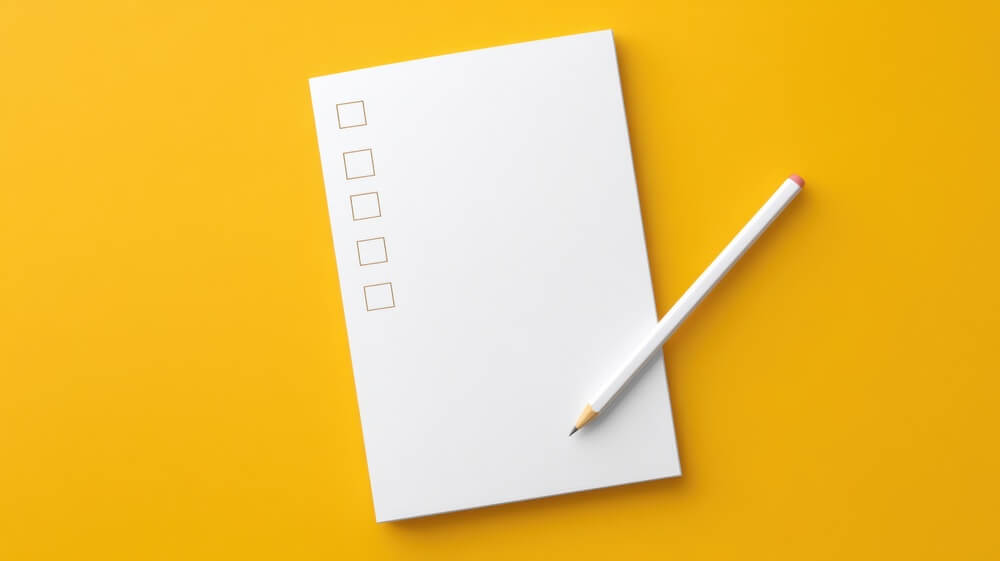
介護保険を利用して購入できる「特定福祉用具」は、主に排泄や入浴の際に使用する、肌に直接触れる福祉用具が対象となっています。これらは衛生面の配慮から、レンタルではなく購入での利用が認められており、利用者の尊厳を保ちながら安全な在宅生活を支援する重要な役割を果たしています。
介護保険で購入できる特定福祉用具一覧
カテゴリー | 品目 | 具体例・説明 |
排泄関連 | 腰掛便座 | ・和式便器を洋式便器に変更するもの ・洋式便器の高さを補う補高便座 ・立ち上がりを補助する機能があるもの ・ポータブルトイレ |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | レシーバー、ホース、タンクなど、尿や便が通る部分。 ※専用パッドなどの消耗品は対象外です。 | |
排泄予測支援機器 | 膀胱の状態を感知して尿量を推定し、排尿のタイミングを本人や介護者に通知する機器。 | |
入浴関連 | 入浴補助用具 | ・入浴用いす(シャワーチェア) ・浴槽用手すり ・浴槽内いす ・入浴台(浴槽の縁にかけて使用) ・浴室内/浴槽内すのこ ・入浴用介助ベルト |
簡易浴槽 | 空気式や折りたたみ式などで、工事を伴わずに設置・移動できる浴槽。 | |
移動関連 | 移動用リフトの吊り具の部分 | 利用者の身体に直接触れるシートやベルト部分。 ※リフト本体はレンタルの対象です。 |
それぞれの品目は、要介護者の日常生活動作を支援し、介護する家族の負担を軽減する目的で選定されています。
腰掛便座には、居室で使用するポータブルトイレ、和式トイレを洋式として使用できるようにする据置式便器、便座の高さが低い場合に立ち上がりを楽にする補高便座、電動やスプリング機能で立ち上がりを補助する便座などがあります。これらは利用者の身体機能や住環境に応じて選択することが可能です。
自動排泄処理装置の交換可能部品については、装置本体はレンタル対象ですが、レシーバーやホース、タンクといった排泄物や利用者の肌に直接触れる部分は購入対象となります。ただし、専用パッドや洗浄液などの消耗品は介護保険の対象外となるため、全額自己負担での購入が必要となることに注意が必要です。
2022年4月からは、新たに排泄予測支援機器も購入対象に加わりました。この機器は、超音波センサーなどで膀胱内の尿量を測定し、排尿のタイミングを利用者や介護者に通知する機能を持っており、排泄の自立支援や介護負担の軽減に役立つものとして期待されています。
入浴補助用具は、浴室での転倒防止や安全な入浴動作を支援するための福祉用具です。購入対象となる具体的な品目は以下のとおりです。
● 入浴用いす(シャワーチェア)
● 浴槽用手すり
● 浴槽内いす
● 入浴台(浴槽の縁にかけて使用)
● 浴室内すのこ
● 浴槽内すのこ
● 入浴用介助ベルト
簡易浴槽については、空気式や折りたたみ式など、簡単に移動できて取水・排水のための工事を必要としないタイプが購入対象となります。これにより、浴室での入浴が困難な方でも、居室などで安全に入浴できる環境を整えることが可能になっています。
移動用リフトの吊り具の部分は、利用者の身体に直接触れるシートやベルトなどが購入対象となります。移動用リフト本体はレンタル対象であり、吊り具部分のみが購入可能という点を正しく理解しておくことが大切です。
この吊り具は、ベッドから車椅子への移乗だけでなく、入浴用やトイレ用など、さまざまな場面での移動を支援するタイプがあります。利用者の体型や身体機能に合わせて適切なサイズや形状を選ぶことで、安全で快適な移乗動作を実現し、介護者の腰痛予防にもつながる重要な福祉用具となっています。

2024年4月の介護保険制度改正により、これまでレンタルのみが認められていた一部の福祉用具について、レンタルと購入のいずれかを選択できる「選択制」が導入されました。この制度改正により、利用者は自身の利用期間や身体状況、経済状況などを総合的に考慮して、より適切な利用方法を選べるようになっています。
選択制の対象となったのは、スロープ(固定用)、歩行器(固定式・交互式)、歩行補助つえ(一部)の3品目です。長期間の利用が見込まれる場合や、頻繁なメンテナンスが不要な品目について、購入という選択肢が加わったことで、利用者にとってより柔軟な福祉用具の活用が可能となりました。
購入の対象となるスロープは、取り付けに工事を伴わない固定用のタイプです。主に室内の敷居やちょっとした段差を解消するために使用され、頻繁に持ち運びをしない固定式のものが該当します。一方、簡単に持ち運びができる可搬型のスロープは、これまでどおりレンタルのみの利用となるため注意が必要です。
利用者の身体状況や住宅環境に応じて、適切な長さや傾斜角度を選ぶことが重要となります。素材についても、滑り止め加工がされているものや、耐荷重を確認したうえで、車椅子や歩行器での移動に適したものを選定することで、安全な在宅生活を支援することができます。
購入の対象となる歩行器は、四脚の先がすべてゴム(杖先ゴムなど)になっている固定式歩行器、または左右の脚を交互に動かして進む交互式歩行器です。これらは体重を支えながら安定した歩行を可能にし、転倒リスクを軽減する重要な福祉用具となっています。
車輪(キャスター)が付いている歩行車については、選択制の対象外であり、従来どおりレンタルでの利用となります。歩行器を選ぶ際は、利用者の握力や上肢の筋力、バランス能力などを総合的に評価し、最も安全に使用できるタイプを選定することが、自立した移動の実現につながります。
購入の対象となる歩行補助つえは、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットフォームクラッチ、そして多点杖(四点杖など)です。これらは前腕部で体重を支えたり、接地面を広くして安定性を高めたりする特殊な構造を持つ杖となっています。
一般的な一本杖(T字杖など)や、医療機関でよく使用される松葉杖は選択制の対象外となるため、購入を希望する場合は全額自己負担となります。身体のバランスを補助し転倒を予防するという杖本来の役割を果たすために、理学療法士や作業療法士などの専門職と相談しながら、症状や身体機能に応じた適切な杖を選択することが大切です。

介護保険を利用して福祉用具を購入する際は、費用負担の仕組みや申請手続きについて事前に理解しておくことが重要です。購入にあたっては、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員といった専門職がサポートしてくれるため、まずは担当者に相談することから始めましょう。適切な福祉用具の選定から購入後の申請まで、一連の流れを把握しておくことで、スムーズな手続きが可能となります。
特定福祉用具の購入には、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で10万円(税込)という上限額が設定されています。自己負担割合は、利用者の所得に応じて原則1割ですが、一定以上の所得がある方は2割または3割の負担となります。年間10万円の上限を超えた購入費用については、全額自己負担での支払いが必要です。
この10万円の購入費用枠は、月々の介護サービス利用限度額とは別枠で設定されているため、他の介護サービスの利用状況に関係なく活用できます。計画的に福祉用具を購入することで、在宅での介護環境を効果的に整備することが可能となっています。
参考:厚生労働省|利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット
福祉用具購入の支払い方法として、原則的には「償還払い」という方式が採用されています。この方式では、利用者がまず購入費の全額を福祉用具販売事業者に支払い、その後市区町村に申請することで、自己負担分を除いた金額が後日払い戻される仕組みとなっています。
一部の自治体では「受領委任払い」という制度も導入されています。こちらは、購入時に利用者が自己負担分のみを事業者に支払い、残りの保険給付分については自治体から直接事業者に支払われる方式です。一時的な経済的負担が大幅に軽減されるため、まとまった資金の準備が困難な方にとって利用しやすい制度となっています。
どちらの支払い方法に対応しているかは自治体によって異なるため、事前に市区町村の介護保険担当窓口や福祉用具販売事業者に確認しておくことが大切です。
介護保険を利用した福祉用具購入の手続きは、以下の5つのステップで進められます。
専門家への相談
ケアマネジャーまたは福祉用具専門相談員に、必要な福祉用具について相談します。
福祉用具の選定と計画書作成
身体状況や生活環境に適した福祉用具を選定し、福祉用具サービス計画書を作成してもらいます。
商品の購入と支払い
都道府県の指定を受けた事業者から福祉用具を購入し、いったん全額を支払います。
自治体への申請
必要書類(領収書、福祉用具のパンフレット等)を添えて、市区町村に購入費の支給申請を行います。
保険給付分の払い戻し
審査後、自己負担分を除いた金額が指定口座に振り込まれます。
最も重要な注意点として、都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は、介護保険の給付対象とならず全額自己負担となってしまいます。必ず指定事業者から購入するよう、事前の確認を怠らないようにしましょう。

おむつや尿取りパッド、介護用食器、介護用衣類といった消耗品や日用品は、残念ながら介護保険の購入対象外となっています。これらは日常的に消費される性質のものであり、福祉用具の定義に該当しないためです。
また、福祉用具があっても、実際の排泄介助や入浴介助、通院の付き添い、買い物代行など、人の手による直接的なサポートが必要な場面は多くあります。介護保険サービスでは時間や内容に制約があり、すべてのニーズに対応できないケースも少なくありません。
このような公的保険でカバーできない用品の購入や、より柔軟できめ細やかな介助サービスを必要とする場合、自費の訪問介護サービス「イチロウ」が選択肢となります。24時間365日対応可能で、利用者一人ひとりのニーズに合わせたオーダーメイドのサービスを提供しており、介護保険サービスと併用することで、より充実した在宅介護環境を実現できます。
介護保険を利用した福祉用具の購入は、排泄や入浴に関連する特定の品目に限定されていますが、利用者の尊厳を保ちながら安全な在宅生活を支援する重要な制度です。2024年4月からは一部の福祉用具でレンタルか購入かを選択できるようになり、より柔軟な利用が可能となりました。購入にあたっては年間10万円の上限があり、申請手続きも必要となりますが、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員がサポートしてくれるため、安心して利用できます。介護保険でカバーできない用品や介助サービスについては、自費サービスの活用も視野に入れながら、最適な介護環境を整えていくことが大切です。
福祉用具の購入を検討する際に、多くの方が疑問に思われる点について、Q&A形式でお答えします。
原則として、同一年度内に同じ種目の福祉用具を再度購入することはできません。ただし、破損した場合や、介護の程度が著しく重くなった場合、用途や機能が異なる場合などは、例外的に再購入が認められることがあります。詳細は担当のケアマネジャーにご相談ください。
修理費用は介護保険の給付対象外となるため、全額自己負担での対応が必要です。メーカー保証期間内であれば無償修理が受けられる場合もあるので、購入時に保証内容を確認しておくことが大切です。
要介護認定の申請前に購入した福祉用具については、介護保険の給付対象となりません。必ず要介護認定を受けてから、指定事業者で購入する必要があります。緊急で福祉用具が必要な場合でも、まず要介護認定の申請を行うことが重要です。