
フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法
介護にまつわるお役立ちコラム

嚥下障害は、高齢者を中心に多くの人が抱える健康課題の一つで、食べ物や飲み物をうまく飲み込めない状態を指します。初期症状を見逃すと誤嚥性肺炎などの深刻な合併症につながることもあるため、早期発見と対策が大切です。
本記事では、嚥下障害の原因や症状、セルフチェック方法に加え、自宅でできる工夫やリハビリ、受診すべき診療科までをわかりやすく解説します。家族や自身の健康に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

嚥下(えんげ)とは、食べ物を認識し、口から胃へ送り込むまでの一連の動作を指します。嚥下障害とは、この一連の動作のどこかに問題が生じ、スムーズに飲み込めなくなった状態のことです。
食べ物を飲み込むプロセスは5つの段階に分かれています。
1.先行期:食べ物を認識する段階
2.準備期:口の中で噛み砕き、飲み込みやすい塊(食塊)にする段階
3.口腔期:舌を使って食塊を喉の奥へ送る段階
4.咽頭期:ごっくんと飲み込み、食道へ送る段階
5.食道期:食道の動きによって胃へ運ぶ段階
まず先行期では視覚や嗅覚で食べ物を認識し、準備期で口の中で噛み砕いて飲み込みやすい塊(食塊)を作ります。続いて口腔期では舌を使って食塊を喉の奥へ送り、咽頭期でごっくんと飲み込んで食道へ運び、最後の食道期で食道の動きによって胃へ送り込まれます。
嚥下障害は、これらのプロセスのいずれかがうまくいかなくなることで発生します。

最近こんなことはありませんか?以下のチェックリストで確認してみましょう。
1.食事中によくむせる、咳き込む 2.飲み込むのに時間がかかるようになった 3.食べ物が口の中に残りやすい 4.食後に声がガラガラ声になる 5.硬いものやパサパサしたものを避けるようになった 6.理由なく体重が減ってきた 7.食事中に疲れを感じる 8.薬が飲みにくくなった 9.夜間に咳き込むことがある
|
複数当てはまる場合は、一度専門家に相談することをおすすめします。

嚥下障害の原因は、その発生メカニズムによって大きく3つのタイプに分類できます。物理的な障害による器質的原因、筋肉や神経の機能低下による機能的原因、そして精神的な要因による心理的原因です。
原因を正しく理解することで、適切な対処法を選択できるようになります。
器質的原因とは、飲み込む動作に必要な器官に炎症や腫瘍があり、食べ物の通り道が物理的にふさがれてしまう状態です。口の中や喉、食道などに何らかの病変があることで、食べ物の正常な通過が妨げられます。
具体的な原因としては、口内炎や咽頭炎、舌炎などの炎症性疾患のほか、食道がんや口腔がん、咽頭がんなどの腫瘍があります。これらの病変により食べ物が通る道がふさがれることで、嚥下障害が引き起こされてしまいます。
機能的原因は、各器官を動かす筋肉や神経に異常があることで、飲み込む動作がうまくできなくなる状態です。これは嚥下障害の中でも最も一般的な原因であり、特に高齢者の方に多く見られます。
代表的な原因として、脳卒中やパーキンソン病などの疾患により筋肉や神経がうまく働かなくなることが挙げられます。また、加齢による筋力低下も機能的原因の一つです。さらに、向精神薬や鎮痛剤などの薬物の影響で各器官の働きが悪くなる場合もあります。
心理的原因とは、身体的な問題はないものの、うつ病や心身症、強いストレスなどの精神的な要因により飲み込みにくさが生じる状態です。喉に違和感や飲み込みにくさを感じ、嚥下がうまくできなくなります。
このような症状は「咽喉頭異常感症」とも呼ばれることがあります。ストレス性の胃潰瘍などの精神疾患により起こることもあり、不安感や緊張状態が続くことで喉の筋肉に影響を与えると考えられています。
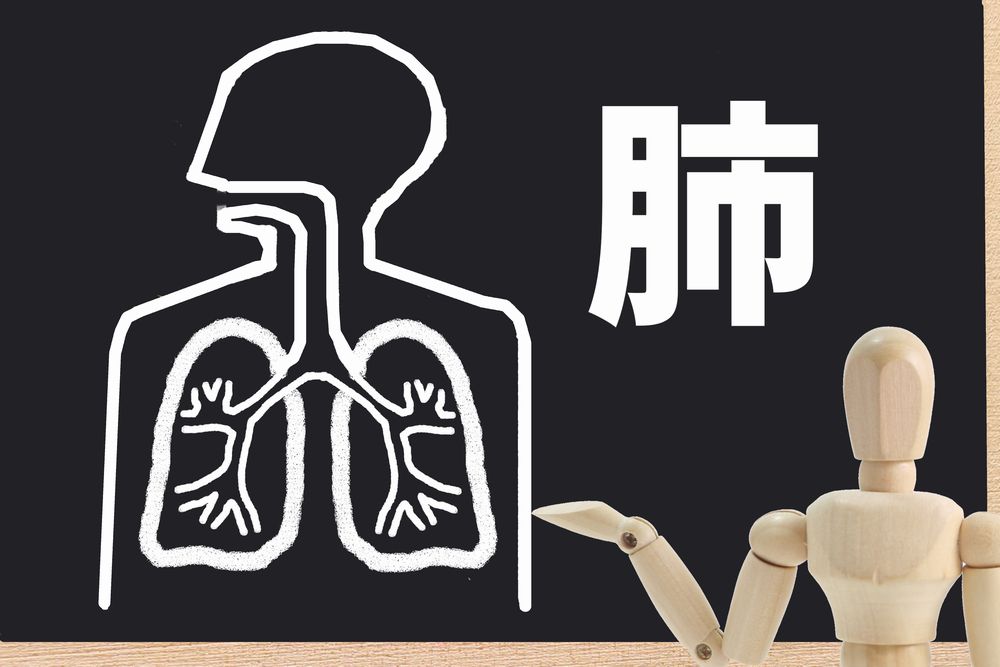
嚥下障害を放置する最大のリスクが「誤嚥性肺炎」です。誤嚥(ごえん)とは、食べ物や唾液が本来通るべき食道ではなく、誤って気管に入ってしまうことを指します。
誤嚥性肺炎は、その際に唾液や食べ物に含まれる細菌が気管を通って肺まで届き、肺で炎症を起こす病気です。通常であれば気管の入り口にフタがされて食道へ送られますが、嚥下障害があると誤って気管に入り込んでしまいます。
厚生労働省によると、高齢者の肺炎のうち7割以上が誤嚥性肺炎となっており、高齢者の死因として多くの割合を占める恐ろしい病気とされています。特に高齢の方や脳梗塞の後遺症、パーキンソン病などの神経疾患を抱えている方は発症リスクが高く、命に関わる危険な合併症といえるでしょう。

口腔機能の低下は、食べられる食物の種類や量を制限し、栄養バランスの乱れから免疫や代謝機能の低下を招きます。その結果、病気にかかりやすく治癒しにくい状態となってしまいます。
しかし、専門家の指導のもとであれば、家庭でも取り組める対処法があります。食事の工夫や口腔ケアの徹底、そして簡単なトレーニングを継続することで、嚥下機能の維持・改善が期待できます。すぐにできることから始めてみましょう。
安全な食事のためには、まず姿勢を整えることが重要です。椅子に深く腰をかけ、背筋を伸ばして座りましょう。食事の形態も調整が必要で、パサパサするものは避け、ゼリー状やペースト状など飲み込みやすい形状に変更します。
一口の量は少なくし、一度にたくさん口に入れないよう注意してください。ゆっくりとよく噛んでから飲み込むことで、誤嚥のリスクを減らせます。食後はすぐに横にならず、2時間程度は座った姿勢を保つことで食べ物の逆流を防げます。
毎食後の歯磨きとうがいを徹底し、口の中を清潔に保つことが誤嚥性肺炎の予防において非常に重要です。口腔内の細菌が少ないほど、万が一誤嚥してしまっても細菌が肺に入り込む量を減らし、肺炎を起こすリスクを大幅に下げられます。
口腔ケアが不十分だと細菌が増殖し、誤嚥性肺炎のリスクが高まってしまいます。入れ歯を使用している場合は、外して丁寧に洗浄することも欠かせません。清潔な口腔環境の維持が、安全な食事につながります。
食事前に行う簡単なトレーニングで、嚥下機能を向上させることができます。首や肩のストレッチから始め、上半身をリラックスさせることで誤嚥しにくい状態を作ります。
頬を膨らませたり、舌を出したり引っ込めたりする運動は、口周りの筋肉の動きをスムーズにし筋力強化を図れます。特に「パタカラ体操」が有名で、「パ」「タ」「カ」「ラ」の4文字を発声することで口・舌の筋肉を効果的に鍛えられる代表的なトレーニング方法です。

セルフケアだけでは限界があり、正確な診断と適切な治療のためには医療機関での受診が不可欠です。嚥下障害が疑われる症状があるときは、早めの医療相談が大切になります。
まず相談すべき診療科として「耳鼻咽喉科」を第一におすすめします。喉や食道の専門家であり、内視鏡検査などを用いて飲み込みの状態を直接観察できるからです。嚥下に関わる重要な器官の診断と治療において、最も適した専門科といえるでしょう。
かかりつけ医がいる場合は、まず相談して適切な専門医を紹介してもらうという選択肢もあります。添付ファイルに記載がないため詳細は記載できませんが、症状や原因によっては他の関連診療科での治療が必要な場合もあります。気になる症状があるときは、医師に早めに相談することが重要です。

嚥下障害の理解と家庭での対処法が分かった一方で、日々の食事介助や本人の状態管理に不安や負担を感じるご家族も多いのではないでしょうか。専門的な知識を持ったヘルパーに食事のサポートをお願いしたい、日々のケアについてプロに相談したいといったニーズにお応えするのが、「イチロウ」の介護サービスです。
「イチロウ」では、嚥下障害のある方の食事介助や口腔ケア、服薬管理、体調管理など、在宅での生活をトータルでサポートできます。お客様一人ひとりに担当ケアコンシェルジュが付き、ご家庭の介護環境を一緒に作り上げていきます。介護保険では対応できないオーダーメイドのサービスで、ご家族の負担軽減を図ります。一人で抱え込まず、まずは気軽に相談してみてください。
嚥下障害は、早期発見と適切な対処により深刻な合併症を防ぐことが可能です。食べ物を飲み込む機能の低下は誰にでも起こりうる問題であり、放置すれば命に関わる誤嚥性肺炎を引き起こすリスクがあります。
しかし、症状のセルフチェックによる早期発見、原因に応じた適切な対処法の実践、専門家への相談により、安全な食事と質の高い生活を維持できます。家庭での食事の工夫や口腔ケア、嚥下体操などの日常的な取り組みを継続することで、嚥下機能の維持・改善が期待でき、本人とご家族がともに安心して過ごすことができるでしょう。
嚥下障害について多くの方が疑問に思われることを、よくある質問としてまとめました。症状の見極め方から医療機関への相談、家庭でのケア方法まで、実際に寄せられる代表的な疑問にお答えしています。
食事中にむせることが週に数回以上ある、飲み込みに時間がかかるようになった、食後に声がガラガラになるなどの症状が複数見られる場合は、早めの受診をおすすめします。特に体重減少や夜間の咳込みがある場合は、誤嚥性肺炎のリスクが高まるため迅速な対応が必要です。
まず食事の安全性を確保することが最優先です。一口の量を少なくし、とろみのついた飲み物や食べやすい形状の食事を提供してください。正しい姿勢での食事を心がけ、食後は座った状態を保つことが重要です。同時に毎食後の口腔ケアを徹底し、誤嚥性肺炎のリスクを減らしましょう。
嚥下体操は毎日継続することで効果が期待できます。理想的には食事前に首や肩のストレッチ、口周りの運動、パタカラ体操を組み合わせて5~10分程度行ってください。無理をせず、できる範囲から始めて徐々に習慣化することが大切です。継続することで嚥下機能の維持・改善につながります。