
フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法
介護にまつわるお役立ちコラム
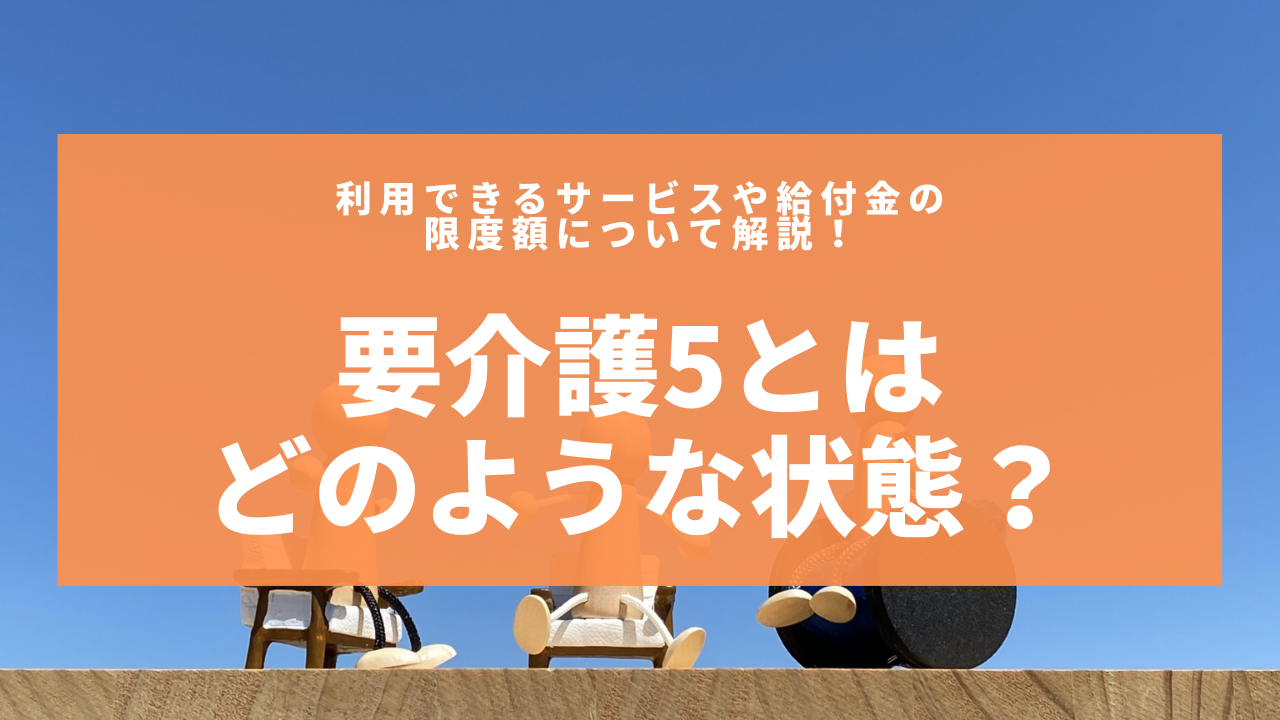
「要介護5と認定されたけど、どのような状態?」
「要介護5の人が受けられるサービスや支給限度額について知りたい!」
と要介護5と認定された方やご家族の方は、思っていませんか?本記事では、「要介護5」の状態や利用できる介護保険サービス内容、給付金の限度額について紹介します。「要介護5」と認定される基準や受けられるサービス内容、保険が適用される支給金額など、気になるポイントを解説していきます。要介護5と認定された方やご家族の方はぜひ最後までご一読ください。
介護が必要な度合いを示す「要介護度」は、自立、要支援(1,2)、要介護(1,2,3,4,5)の8段階に分けられます。そして要介護5とは、要介護認定の中で最も症状の重い状態のことを指します。また要介護は、年齢や身体機能、認知症の進行具合によって、費用や介護内容も大きく異なります。そこで今回は、要介護認定の中でも最も重い状態「要介護5」について詳しく解説します。
要介護5の基準例をまとめると以下の通りです。
要介護5の場合は、一日中ほとんど寝たきりのことが多く、立ち上がって歩くことができない状態です。そして、掃除や買出しなどの家事ができないだけではなく、食事や排泄、入浴など日常生活のほぼ全てに介助が必要です。さらに筋力の低下により、食べ物や飲み物を飲み込むことが困難な方もいます。また、要介護5になる原因の多くは脳卒中や認知症とされています。そのため、理解力や思考力の低下や意思疎通が困難になるケースが多いです。
要介護4も要介護5と同様に重度の介護が必要とする状態です。そして要介護5と同じように日常生活において介護が必要という点では、大きな違いはありません。しかし要介護4では日常生活において、介護があれば自分でできることが多いですが、要介護5になると、全面的な介護が必要になります。そして、要介護5は寝たきりの状態が長く、動作や行動の1つ1つに介護が必須です。また要介護5では、理解力も著しく低下してしまい、意思疎通が困難な状態になります。そのため、要介護4と要介護5の違いとしては、
で見分けられることがあります。
要介護5は、要介護度の中で最も症状の重い状態のため、自宅介護や施設入居、介護用具のレンタルなどが可能です。また要介護5では、区分支給限度基準額は1ヶ月あたり36万2,170円であり、介護保険が適用されます。これらのサービス内容や支給限度額について理解しておくことで適切な介護を受けることができるでしょう。そこで、ここでは要介護5の状態の方が受けられる介護保険サービスの内容や支給限度額について詳しく解説していきます。
要介護5の方が利用できる介護サービスの種類を紹介します。
自宅で受けられるサービス
施設に通うことで受けられるサービス
短期間の宿泊
地域密着型のサービス
福祉用具の使用
上記のように要介護5の方が受けられるサービスは、在宅介護や施設利用、福祉用具のレンタルなど幅広くあります。このように要介護5の方は多種多様な介護サービスが受けられるため、自身の状態に合った介護サービスを利用することがおすすめです。
要介護者には、要介護度別に「区分支給限度額」が定められています。区分支給限度額とは、介護保険から給付される限度額のことであり、要介護ごとに金額が異なります。その中でも要介護5の場合、区分支給限度基準額は1ヶ月あたり36万2,170円です。つまり、自己負担額が以下のようになります。
そのため、1ヶ月あたり36万2,170円までのサービスであれば、1割から3割負担で利用することが可能です。しかし限度額を超えて介護保険サービスを利用する場合は、全額が自己負担になりますので、注意しましょう。また具体的な金額は地域によって異なる場合があるため、詳細はケアマネジャーや市区町村の窓口に確認することがおすすめです。
要介護5の方は、以下のような特徴の介護施設が利用できます。
介護付き有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
特別養護老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅(通称:サ高住)
ケアハウス
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
要介護5では、基本的に施設への入居が可能です。また特別養護老人ホームのように、要介護5の認定を受けている場合、要介護3,4の方よりも優先的に入居できる場合があります。
今回は「要介護5」の状態や利用できる介護保険サービス内容、給付金の限度額について紹介しました。改めて、本記事のポイントを以下にまとめます。
要介護5の状態は、常に介護が必要になるため、自分に合う施設や介護サービスを選択することが重要です。そのため、担当のケアマネジャーやお近くの介護施設に相談してみてはいかがでしょう?