
フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法
介護にまつわるお役立ちコラム

親の介護を続ける中で、「そろそろ施設にお願いすべきかもしれない」と感じる場面があるかもしれません。しかし、施設に任せることへの迷いや罪悪感、入居後の後悔など、決断には多くの不安が伴います。重要なのは、施設入居は介護の「失敗」ではなく、本人と家族の生活を守るための「積極的な選択」と捉えることです。
本記事では、親を施設に入れるタイミングの見極め方から、スムーズな入所のための手順、注意点までをわかりやすく解説。後悔のない選択をするために、ぜひ参考にしてください。

在宅での介護が難しくなり、施設への入居を具体的に検討すべきタイミングについて、客観的な判断基準を提示します。公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、要介護5の方を介護する場合、63.1%の方が「ほとんど終日」を介護に費やしているという現実があります。この状況は誰にでも起こりうることであり、決して特別なケースではありません。
親を施設に入れることは、決してネガティブな選択ではありません。ご本人と家族の生活を守り、より安全で質の高い介護環境を整えるための重要な選択肢の一つです。以下で具体的な判断基準を見ていきましょう。
参考:公益財団法人 生命保険文化センター|誰が介護している?介護にかける時間は?
介護者自身の状態を客観的に見つめ直すことが重要です。「親のためにできることはしてあげたい」と頑張りすぎてしまう気持ちは分かりますが、介護者が倒れてしまっては元も子もありません。身体的な限界のサインとして、十分な睡眠がとれない、持病が悪化した、介護が原因で怪我をしたなどが挙げられます。精神的な限界では、自分の時間がなくなり精神的に追い詰められる、ささいなことでイライラしてしまう状況が続くと、介護うつや虐待につながる恐れもあります。
介護疲れによる共倒れのリスクを避けるため、自分自身の健康状態を客観視する必要があります。休息が取れず、プライベートな時間も確保できない状況が続く場合は、無理をせず介護の専門家や施設サービスを頼ることが大切です。
加齢による身体機能の低下により、自宅での生活には多くの危険が潜んでいます。たとえば、転倒による骨折や食事中の誤嚥(ごえん)リスクです。専門的な医療ケアが必要になった場合、たんの吸引、経管栄養、インスリン注射、ストーマ管理などは在宅での対応が困難になるケースがあります。これらの医療的ケアは、適切な知識と技術がないと命に関わる重大な事故につながる可能性があります。
「いつ何が起こるか分からない」という不安の中で生活するのは、本人にとっても家族にとっても大きなストレスとなります。ご本人が一人でいる時間に危険が伴うようになり、常時誰かの見守りが必要だと感じた時が、施設入居を検討する重要なタイミングといえるでしょう。
認知症の進行に伴って現れるBPSD(認知症の行動・心理症状)には注意が必要です。暴言・暴力、徘徊、火の不始末、金銭管理ができないなどの症状により、介護者が身の危険を感じたり、ご本人が事故に巻き込まれたりするリスクが高まります。
認知症の方への対応で最も大切なのは、本人の尊厳を保ちながら安全を確保することです。しかし、家族だけ24時間続けることは現実的に困難な場合があります。認知症ケアは専門的な知識や対応が求められます。家族だけで抱え込まず、認知症ケアに特化した施設(グループホームなど)の専門家の力を借りる選択肢があることを理解しておくことが重要です。
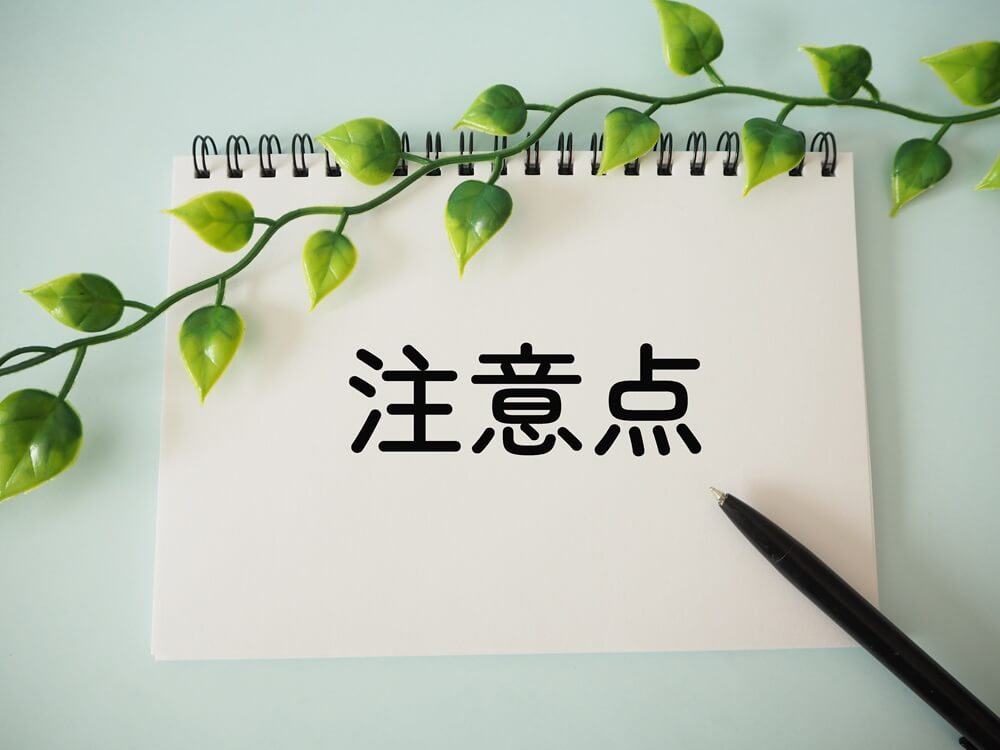
施設入所を成功させるためには、適切な手順を踏むことが不可欠です。焦って決断すると、あとで後悔することになりかねません。ご本人の意思を尊重しながら、家族全員が納得できる選択を行うための具体的なステップを解説します。
施設入居を検討する最初のステップとして、必ず入居するご本人を含めた家族全員で話し合うことが重要です。家族会議では以下の項目を明確にしておく必要があります。
| 確認事項 | 具体的な内容 |
| 本人の意思 | どのような環境で過ごしたいか、誰に介護してもらいたいか、お金の使い道の希望など |
| 家族の役割分担 | 身元引受人・連帯保証人を誰が担うか、緊急時の連絡先や駆けつけ担当など |
| 費用面の確認 | 親の年金や貯蓄額、不足分を家族がどう援助できるかなど |
話し合いの際は、決して結論を急がないことが大切です。「今すぐ決めなければ」という焦りは禁物です。ご本人の気持ちに寄り添いながら、家族全員が納得できるまで対話を重ねる姿勢が大切です。
家族会議で出た意見をもとに、入居する施設に求める希望条件を整理しましょう。具体的な情報収集の方法は以下の通りです。
【情報収集の方法】
希望条件に優先順位をつけておくと、施設を絞り込みやすくなります。ただし、「あれもこれも」と条件を多くしすぎると思うように進まない可能性が出てきます。そのため「これだけは譲れない」という条件を明確にしておくことが大切です。
パンフレットやウェブサイトの情報だけで判断せず、必ず現地へ足を運んで見学することが重要です。施設見学の際は以下のチェックリストを活用しましょう。
【確認すべきチェックリスト】
可能であれば、短期入所(ショートステイ)や体験入居を利用し、食事や夜間の様子など、実際の生活をご本人が体験してみることをおすすめします。「思っていたのと違う」というミスマッチを防ぐために、体験入居は非常に有効な手段です。
ご本人が入居を拒否する背景には、住み慣れた家を離れたくない、他人の世話になりたくない、見捨てられる不安などがあります。無理に説得するのではなく、「元気に長生きしてほしいから」というポジティブな理由を伝えることが大切です。
施設のパンフレットを見ながら、レクリエーションやイベントなど楽しい面を伝えたり、入居後も頻繁に面会に行くなど、関係性が変わらないことを約束したりすることで、ご本人の不安を軽減できます。「施設に入ったら縁が切れる」のではなく、「より良い環境で一緒に過ごす時間を大切にする」というポジティブなイメージを持ってもらうことが重要です。
家族間の話し合いで行き詰った場合は、ケアマネジャーやかかりつけ医といった第三者に間に入ってもらうことで、ご本人が冷静に話を聞き入れるきっかけになる場合があります。

施設入居だけでなく「質の高い在宅サービスを利用する」という選択肢があり、「イチロウ」のサービスがその一助となります。介護保険制度では対応が困難なニーズに柔軟に応えられる点が、イチロウの「介護保険外サービス」の大きな特徴です。
24時間365日対応により、早朝や夜間、土日祝日を問わず、必要な時にいつでもサービスを利用できます。サービス内容は、ご自宅での介護や家事はもちろん、病院内での付き添いや外出支援など、幅広いご要望に対応可能です。迅速な対応力も特徴で、最短でご依頼当日からヘルパーの手配ができ、急な要望にも応えられる体制を整えています。さらに、看護師の資格を持つスタッフが、たんの吸引や経管栄養などの医療行為にも対応できます(※東京23区限定)。
「住み慣れた自宅で暮らし続けたい」というご本人やご家族の想いに寄り添い、在宅介護の限界を感じる前に検討する価値があるサービスといえるでしょう。
親の介護において施設入居を検討することは、家族全員の幸福を守るための重要な選択です。介護者の心身の限界や安全確保の困難化が深刻化する現代において、適切なタイミングで専門的なケアを受けられる環境を整えることが必要不可欠となっています。施設入居の手順を正しく理解し、ご本人の意思を尊重した話し合いを重ねることで、罪悪感を抱くことなく最適な介護選択を実現できるでしょう。
施設入居を検討する際に多くの方が抱く疑問や不安について、具体的な解決策とともにお答えします。
施設入居を検討する際に罪悪感を抱くのは、親を大切に思うからこその自然な感情です。施設入居は介護の放棄ではなく、専門家の力を借りて、より安全で質の高い生活環境を整えるための「前向きな選択」です。入居後も、面会に行ったり、施設のイベントに一緒に参加したりと、家族だからこそできる関わり方は多くあり、関係が終わるわけではありません。
後悔を避けるためには、入居を決める前に、ご本人と家族がとことん話し合い、全員が納得することが最も重要です。介護保険制度は、介護を社会全体で支えるための仕組みであり、家族だけで全てを抱え込む必要はありません。入居後は、施設スタッフを「介護のパートナー」と捉え、ご本人の様子について密に情報交換をしながら、一緒にケアを行っていく姿勢が大切です。
認知症の進行には個人差があるため一概には言えませんが、「介護者が大きな負担を感じ、在宅での介護を安全に続けることが困難になった時」が目安です。可能であれば、認知症の診断を受けた早い段階から、地域包括支援センターなどに相談し、情報収集を始めておくことをおすすめします。認知症の方が入居できる施設には有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどがありますが、症状の程度によっては入居が難しい場合もあるため、各施設への事前確認が不可欠です。