
フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法
介護にまつわるお役立ちコラム

せん妄は、注意力や思考力の低下、見当識障害、意識レベルの変動を特徴とする一時的な精神状態の変化です。高齢者の入院患者に多く見られ、認知症と混同されやすいものの、適切な治療により回復が期待できる可逆的な病態とされています。
本記事では、せん妄の基本的な定義から認知症との違い、発症の原因やメカニズム、夜間せん妄の特徴、予防と早期発見のポイントまで、せん妄について知っておくべき重要な情報をわかりやすく解説します。患者さんやご家族が適切な理解と対応ができるよう、ぜひ参考にしてください。

せん妄は、注意力や思考力の低下、見当識障害、意識レベルの変動を特徴とする異常な精神状態です。病名ではなく、さまざまな原因によって一時的に生じる錯乱状態を指します。せん妄の重要な特徴として、急性に発症し、症状の程度が時間とともに変動することが挙げられます。
多くの場合、原因を特定して適切に治療すれば症状は改善する可逆的な病態とされています。
せん妄の中心的な症状は「注意の障害」と「意識の障害」に分けられます。
以下の表で整理して説明します。
| 障害の種類 | 主な症状 | 具体的な現れ方 |
| 注意の障害 (注意力および思考力の低下) | 集中力の低下、持続的な注意の困難 | 何かに集中することができない、新しい情報を処理できない、最近の出来事を思い出せない |
| 意識の障害 (見当識の低下) | 見当識障害、妄想や幻覚 | 日時や場所がわからない、何が起こっているか理解できない、妄想や幻覚が現れる |
せん妄は症状の現れ方によって3つのタイプに分類されます。
せん妄の特徴的な点は、意識レベルが1日の中で大きく変動することです。数分前は正常な精神状態だった人が、突然せん妄状態になることもあり、継続的な観察が必要となります。
せん妄の発症メカニズムは完全には解明されていませんが、主要な要因として脳内の酸化的代謝の可逆的障害と複数の神経伝達物質の異常、特にアセチルコリンの作用不足が関与しています。
つまり脳がエネルギーを作る仕組みが一時的にうまく働かなくなることと、脳の神経同士が連絡を取り合うための化学物質、特に記憶や注意力に重要な「アセチルコリン」という物質が不足することが、せん妄を引き起こす主な原因だということです。
ストレスが重要な誘因となり、交感神経の緊張を高め、副交感神経の緊張を抑制することでコリン作動性機能が障害されます。高齢者は特にコリン作動性伝達の低下に敏感であるため、せん妄のリスクが高くなります。
最終的には、原因を問わず大脳半球または視床および脳幹網様体賦活系による覚醒機序が阻害されることで、せん妄の症状が現れると考えられています。

せん妄と認知症は、どちらも認知機能に影響を及ぼす病態ですが、発症の仕方や症状の特徴、予後に大きな違いがあります。せん妄は急性に発症し可逆的である(元に戻る可能性がある)一方、認知症は慢性的に進行し基本的に不可逆的です。
適切な診断と対応のため、両者の違いを正しく理解することが重要になります。
| せん妄 | 認知症 | |
| 発症の仕方 | 急激に発症、数時間から数日で進行 | 徐々に発症、ゆっくりと進行 |
| 初期症状 | 幻覚、妄想、興奮 | 記憶障害 |
| 主な症状 | 注意散漫、集中力欠如(意識の障害) | 時間や場所などの感覚が薄れる(記憶の障害) |
| 日中の変動 | 夕刻〜夜間に悪化することが多い | 変動は少ない |
| 症状の持続期間 | 数時間〜数日 | 永続的 |
せん妄は突然発症し、数時間から数日で症状が進行する急性の病態です。多くの場合、発症した時点を特定できるという特徴があります。初期症状として幻覚、妄想、興奮が現れることが一般的です。
一方、認知症は一般的にゆっくりと進行し、いつ始まったのか特定することが困難とされています。認知症の初期症状は記憶障害から始まることが多く、せん妄とは明確に異なる症状パターンを示します。
せん妄では意識障害が生じますが、認知症では意識はおおむね正常な状態を保ちます。これが両者を鑑別する重要なポイントの一つです。
症状の変動性にも大きな違いがあります。せん妄は1日の中で症状が変動し、特に夕刻から夜間にかけて症状が悪化することが多く見られます。症状は数分から数時間で変化することもあります。対照的に、認知症では日中の症状変動は少なく、比較的安定した状態が続きます。
せん妄は原因となる病気や薬剤への対処により、認知機能の回復が可能な病態です。適切な治療を行うことで、多くの場合症状の改善が期待できます。
認知症は一度発症すると、基本的に認知機能が戻らず進行していく特徴があります。治療により進行を遅らせることは可能ですが、根本的な回復は困難とされる不可逆的な病態です。
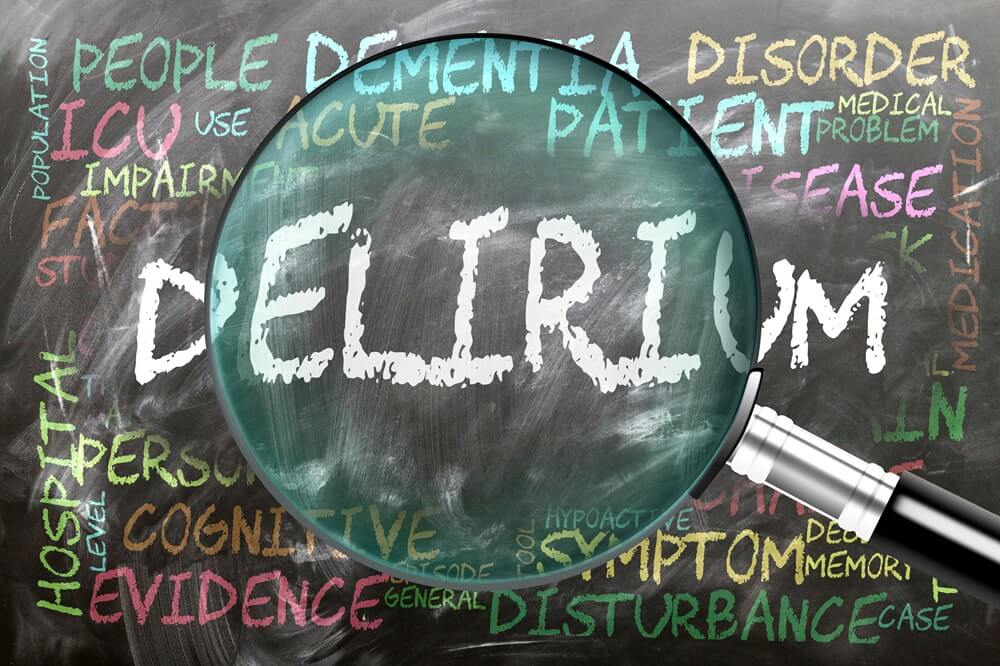
せん妄の発症には複数の要因が複雑に絡み合っています。単一の原因だけでなく、患者の体質的な要因、直接的な誘因、環境的な促進因子が相互に作用することで発症に至ります。
特に高齢者と若者では原因となる要因に違いがあり、入院や手術といった医療環境も重要な誘発要因となることが知られています。
せん妄の発症には準備因子、直接因子、促進因子の3つが関与します。
【準備因子(せん妄になりやすい要因)】
【直接因子(脳機能に直接影響する要因)】
【促進因子(環境や心理的要因)】
高齢者では尿路感染症、便秘、感覚遮断などの比較的軽い病態がせん妄の原因となります。脱水や睡眠不足、痛み、膀胱カテーテルの使用といった日常的な要因でも発症しやすい特徴があります。
若者のせん妄では、レクリエーショナルドラッグの使用や生命を脅かす全身性疾患が主な原因となります。高齢者は薬剤への感受性が大幅に高まっており、特に抗コリン作用のある薬剤に対して敏感に反応するため、薬剤性せん妄のリスクが高くなります。
ICUなどの慣れない環境は、窓や時計のない隔離された空間となり、感覚からの刺激が減少することで見当識の混乱を引き起こします。感覚遮断がせん妄の重要な誘因となります。
手術によるストレス、麻酔薬の使用、術後の鎮痛薬投与がせん妄発症の直接的な原因となります。また、夜間の検査や治療による睡眠妨害、モニターの信号音、インターホン、廊下からの声やアラーム音などの環境要因も睡眠を妨げ、せん妄を誘発する要因として作用します。

せん妄の症状は特に夜間に現れやすく、「夜間せん妄」と呼ばれる状態があります。昼間は比較的落ち着いているにも関わらず、夜になると興奮や混乱が強くなる特徴的なパターンを示します。
夜間せん妄は睡眠覚醒リズムの障害と密接に関連しており、認知症患者では特に発症リスクが高くなることが知られています。
外が暗くなることで電気をつけないと周囲が見えにくくなり、患者は不安や恐怖、孤独を感じやすくなります。この視覚的な制限が心理的なストレスを引き起こし、せん妄の誘因となります。
夜間には感覚からの刺激が減少するため、見当識の混乱が生じやすくなります。リスクのある患者では、このような感覚刺激の減少がせん妄を直接的に誘発する要因となります。また、睡眠と覚醒のリズムが崩れることで昼夜逆転が起こり、夜間に症状が強く現れる特徴的なパターンが形成されます。
海外では、アルツハイマー型認知症患者の約10%が同時にせん妄を発症するという研究結果があります。認知症に合併したせん妄は、入院中の認知症患者の最大49%に発生する可能性があるとされています。
認知症患者ではせん妄のリスクが高まりますが、症状が似ているため見逃されやすいという問題があります。せん妄を認知症の一症状と勘違いし、適切な治療が遅れてしまうケースも少なくありません。両者の鑑別診断が重要な課題となっています。
せん妄により睡眠と覚醒のサイクルが逆転し、昼間に眠って夜間に起きている状態になります。この昼夜逆転はせん妄の最も代表的な症状の1つとされています。
患者は睡眠中も落ち着きがなく、正常な睡眠パターンを維持できません。長期的な睡眠不足は、それ自体がせん妄の誘因となる悪循環を形成します。睡眠覚醒リズムの障害は、せん妄の症状を悪化させる重要な要因として認識されています。
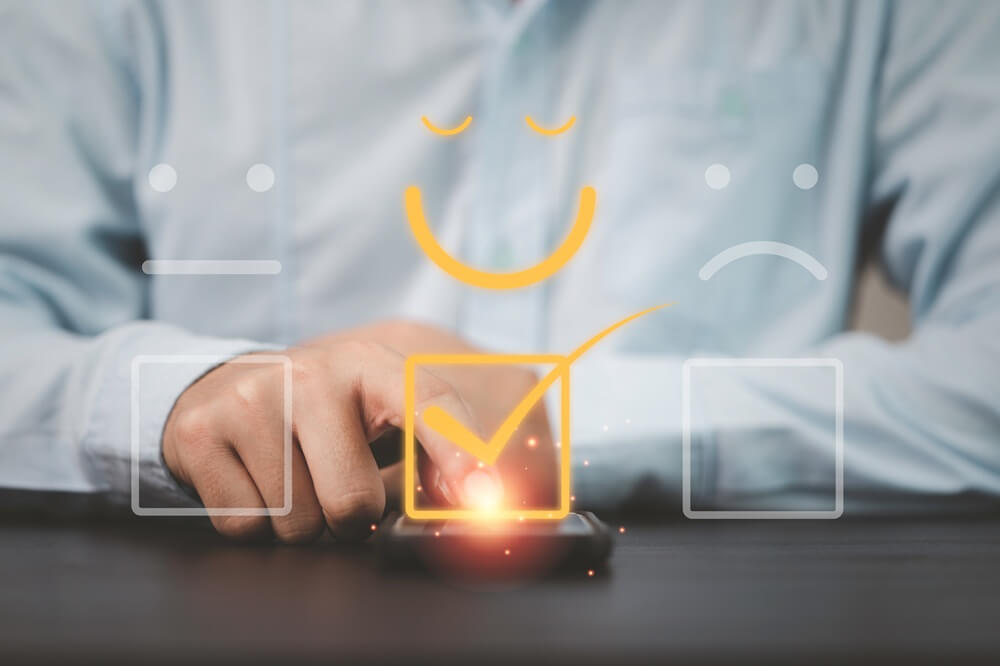
せん妄は適切な予防策により発症リスクを軽減できる病態です。環境の整備、生活リズムの調整、早期の症状発見が重要な対策となります。
特に高齢者では軽微な変化でもせん妄を誘発する可能性があるため、家族や介護者による日常的な観察と支援が予防の鍵となります。
静かで落ち着いた明るい環境を確保し、見当識の手がかりとなるカレンダー、時計、家族の写真などを設置することが効果的です。十分な明るさを維持し、患者が自分の置かれた状況を理解しやすい環境を整えます。
日中は陽の光を浴びて活動し、夜は眠るといった規則正しい生活リズムをつくることが重要です。昼夜逆転の予防につながります。感覚障害を最小限に抑える工夫として、補聴器の電池交換や眼鏡の使用を奨励し、患者が周囲の情報を適切に受け取れるよう配慮します。
記憶または注意の障害がみられる高齢患者では、全例でせん妄を考慮すべきとされています。急な精神状態の変化、特に注意力の低下や意識レベルの変動を注意深く観察することが大切です。
高齢者では寡黙で引きこもりになる場合があり、この変化がうつ病と誤診される可能性があります。活動的だった人が急に内向的になった場合は要注意です。COVID-19などのウイルス感染症では、発熱や咳などの典型的な症状がなく、せん妄が初発症状として現れることがあります。
薬剤の適切な管理と服用タイミングのコントロールが重要です。必要な薬を適切なタイミングで必要な量だけ服用するよう、家族が支援することで薬剤性せん妄の予防につながります。
頻繁な見当識の強化と励まし、患者との会話が見当識の維持に役立ちます。家族が見舞いや面会を通じて患者と話すことで、患者の不安軽減と認知機能の維持が期待できます。質の良い睡眠がとれるよう睡眠環境を整備し、日中は買い物への同行などの適度な運動を取り入れることも効果的な予防策となります。

せん妄は早期の意識的なケアにより症状を和らげることが可能な病態です。しかし、在宅でのせん妄ケアには専門的な知識と24時間体制での対応が必要となります。
イチロウの訪問介護サービスは、せん妄ケアにおいて重要な役割を果たします。介護資格や経験を持った専門職によるヘルパー手配率96%を実現し、認知症の症状の度合いに関わらず対応が可能です。24時間365日対応により、夜間せん妄などの緊急時にも迅速な支援を提供できます。
可能な限り1人のヘルパーでのサービス提供を心がけることで、患者との信頼関係を築きながら継続的なケアを実現します。これにより、介護をする家族の仕事やプライベートを犠牲にすることなく、要介護度が高くなった場合でも継続的なサポートが可能となります。
高齢化社会を迎える現代において、せん妄を正しく理解し適切に対応することは、患者本人と家族にとって重要な課題です。せん妄は一時的な意識障害でありながら、認知症と混同されやすく、適切な診断と治療が遅れがちな病態です。しかし、原因を特定して早期に対処すれば多くの場合で症状の改善が期待できます。認知症との違いを理解し、3つの発症因子を把握して予防策を講じることで、患者の安全を守り、より良い治療環境を実現することができるでしょう。
せん妄について、患者さんやご家族からよく寄せられる質問をまとめました。せん妄の基本的な疑問から予防方法まで、わかりやすくお答えしています。
せん妄は急激に発症し、意識障害を伴う一時的な状態です。認知症は徐々に進行し、基本的に不可逆的な病態です。せん妄は原因を治療すれば回復可能ですが、認知症は進行を遅らせることはできても根本的な回復は困難とされています。
注意力の低下、集中困難、見当識障害(時間や場所がわからない)から始まることが多いです。幻覚や妄想、興奮状態が現れることもあります。症状は1日の中で変動し、特に夕方から夜間にかけて悪化する傾向があります。
昼間は比較的落ち着いているのに、夜間になると興奮や混乱が強くなる状態です。外が暗くなることで不安や恐怖を感じやすくなり、感覚刺激の減少が誘因となります。睡眠覚醒リズムの障害と密接に関連しています。
適切な環境づくりと生活習慣の管理により予防効果が期待できます。カレンダーや時計の設置、規則正しい生活リズム、薬剤の適切な管理、十分な水分摂取などが有効です。家族による見当識の強化と励ましも重要な予防策となります。
急な精神状態の変化や注意力の低下を感じたら、すぐに医師や看護師に相談してください。特に高齢者では「いつもと違う」と感じた場合は早期の相談が重要です。早期発見・早期対応により症状の改善が期待できます。