
フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法
介護にまつわるお役立ちコラム

骨粗鬆症は骨の量が減少し、骨がもろくなることで骨折しやすくなる疾患です。自覚症状が乏しいため気づかないうちに進行し、軽い転倒でも重篤な骨折を引き起こし、要介護状態の原因となることがあります。
本記事では、骨粗鬆症の問題点や危険因子から、予防に効果的な食事療法と運動療法まで包括的に解説します。適切な栄養摂取と運動習慣により骨密度の低下を防ぎ、健康な骨を維持する方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

骨粗鬆症は骨の量が減少し、骨がもろくなることで骨折しやすくなる疾患です。この病気は自覚症状が乏しいため、多くの方が気づかないうちに進行してしまいます。軽い転倒でも重篤な骨折を引き起こし、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
以下では、骨粗鬆症が引き起こす具体的な問題点と、どのような方がリスクを抱えているかについて解説します。
参考:公益財団法人骨粗鬆症財団|豊かな人生に丈夫な骨づくり~骨粗鬆症対策は早期発見・早期予防~
骨粗鬆症では、股関節(太ももの付け根)、手首、脊椎(背骨)、肩の4つの部位で骨折が起こりやすくなります。特に股関節の大腿骨頚部骨折は要介護状態の主要な原因となり、滑る、つまずく、バランスを崩すといった軽微な外力でも発生します。脊椎の圧迫骨折では背骨を構成する椎体という骨がつぶれて背中が丸くなり、内臓圧迫による消化不良や便秘が生じます。
骨粗鬆症による骨折は、骨の再生能力低下と骨密度不足により治癒が遅延し、変形が残りやすいのが特徴です。
骨粗鬆症の危険因子は多岐にわたります。
以下の表に主要な危険因子をまとめました。
| カテゴリー | 危険因子 | 詳細 |
| 身体的特徴 | 性別 | 女性は男性より高リスク(50歳以上女性の約20%が発症) |
| 年齢 | 加齢とともにリスク増加 | |
| 体型 | 低身長、細身の体形 | |
| 家族歴 | 遺伝的要因 | 両親の股関節骨折歴など |
| ホルモン関連 | 閉経 | 早期閉経(50歳前後) |
| 性腺機能 | 性腺機能低下症 | |
| 男性ホルモン | テストステロン値低下 | |
| 生活習慣 | 喫煙 | 骨量減少を促進 |
| 飲酒 | 過度の飲酒 | |
| 運動不足 | 体を動かさない生活習慣 | |
| 日光浴不足 | ビタミンD生成不足 | |
| 栄養面 | カルシウム不足 | 骨の材料不足 |
| ビタミンD不足 | カルシウム吸収に必要 | |
| タンパク質不足 | 高齢者で摂取量不足 | |
| 嗜好品・食習慣 | カルシウム不足 | 骨の材料不足 |
| ビタミンD不足 | カルシウム吸収に必要 | |
| タンパク質不足 | 高齢者で摂取量不足 | |
| 嗜好品・食習慣 | カフェイン | コーヒーの多飲 |
| 加工食品 | インスタント食品の頻繁摂取 | |
| 基礎疾患 | 内分泌疾患 | クッシング病、副甲状腺機能亢進症など |
| その他の疾患 | 慢性腎臓病、関節リウマチなど | |
| 薬剤 | 長期使用薬 | コルチコステロイド、抗てんかん薬など |
女性は男性より圧倒的にリスクが高く、50歳以上の女性では5人に1人が発症します。カルシウムやビタミンDの摂取不足、日光浴不足による体内ビタミンD生成不足が骨量減少を促進し、体を動かさない生活習慣も骨への負荷不足により骨量減少を招きます。
閉経後のエストロゲン急速減少は骨粗鬆症の最重要原因です。50歳前後の閉経を境にエストロゲン分泌が低下し、骨分解が骨形成を上回る状態になります。男性でもエストロゲン値低下が骨粗鬆症に関連し、テストステロン値の低下も一因となります。骨密度は20歳頃にピークを迎えた後徐々に低下し、ホルモン値変化による影響は年齢とともに顕著になります。

骨粗鬆症の予防には、適切な栄養摂取が欠かせません。特にカルシウム、ビタミンD、ビタミンKの3つの栄養素は骨の形成と維持に重要な役割を果たします。また、骨の構成成分であるタンパク質も十分に摂取する必要があります。
一方で、骨密度低下を促進する可能性がある食品や嗜好品については摂取を控えることが大切です。バランスの良い食事を規則的に摂ることで、健康な骨を維持できます。
骨粗鬆症予防に重要な3つの栄養素を豊富に含む食品は、以下のとおりです。
| 栄養素 | 食品カテゴリー | 具体的な食品 |
| カルシウムを多く含む食品 | 乳製品 | 牛乳、ヨーグルト |
| 魚介類 | 小魚、干しエビ | |
| 野菜類 | 小松菜、チンゲンサイ | |
| 大豆製品 | 豆腐、豆類 | |
| その他 | ‐ | |
| ビタミンDを多く含む食品 | 魚類 | サケ、ウナギ、サンマ、メカジキ、イサキ、カレイ |
| きのこ類 | シイタケ、キクラゲ | |
| 卵類 | 卵 | |
| その他 | ‐ | |
| ビタミンKを多く含む食品 | 発酵食品 | 納豆 |
| 緑黄色野菜 | ホウレンソウ、ブロッコリー | |
| 葉物野菜 | 小松菜、ニラ、サニーレタス、キャベツ |
カルシウムとビタミンDを同時に摂取することで、腸管でのカルシウム吸収率が向上する相乗効果があります。食品からの摂取が困難な場合はサプリメントの活用も有効で、胃酸分泌抑制薬を服用している方にはクエン酸カルシウムが適しています。骨代謝を盛んにし、骨の形成を促すため、これらの栄養素をバランスよく摂取することが重要です。
参考:厚生労働省|毎日の食事で骨粗鬆症に備える~骨を強くする栄養と食事について~
高齢者ではタンパク質摂取量が不足する傾向があり、これが骨密度低下を助長します。食の好みの変化や小食により摂取量が減少し、骨の健康に悪影響を与えています。
タンパク質は骨の構成成分として不可欠であり、骨代謝においても重要な役割を果たします。骨の形成と維持には十分なタンパク質が必要で、不足すると骨密度の低下につながります。
適切なタンパク質摂取のためには、肉類、魚類、大豆製品、乳製品などをバランスよく摂取することが大切です。高齢者は意識してタンパク質を摂取し、骨の健康維持に努める必要があります。
骨密度低下を促進する可能性がある食品・嗜好品は以下のとおりです。
これらの食品・嗜好品は、カルシウムの吸収阻害や骨代謝への悪影響を及ぼすメカニズムがあります。過度の摂取は骨の健康を損なう可能性があります。
適度な摂取を心がけ、コーヒーは1日2~3杯程度に留めることが望ましいです。代替品として、カルシウムを多く含む飲み物や食品を選択することで、骨の健康をサポートできます。
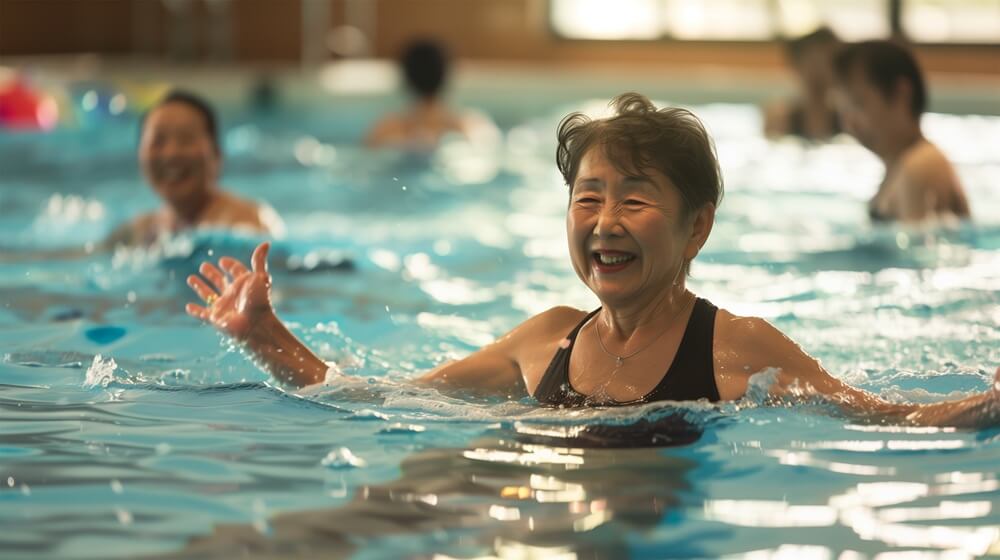
骨は負荷がかかるほど骨をつくる細胞が活発になり、強くなる性質があります。運動療法は骨粗鬆症予防において食事療法と同様に重要な要素です。適切な運動により骨密度を増加させ、転倒予防やバランス感覚の向上も期待できます。
運動の種類により骨への効果が異なるため、目的に応じた運動選択が必要です。継続的な運動習慣の確立により、骨の健康維持が可能になります。
| 運動の種類 | 運動例 | 骨密度への効果 | 適応・注意点 |
| 体重負荷運動 | ウォーキング、ジョギング、階段昇降 | 骨密度増加に効果的 | 週2~3回、30分程度 |
| 非体重負荷運動 | 水泳 | 骨密度増加効果は限定的 | 筋力・バランス向上には有効 |
| 筋力トレーニング | ウェイトトレーニング | 骨の強度向上 | 体調に合わせて実施 |
| バランス運動 | 片脚立ち | 転倒予防効果 | 壁やテーブルを支えに |
| ストレッチ | ふくらはぎ、背筋伸ばし | 筋肉の柔軟性向上 | 左右30~40秒ずつ |
週2~3回、ちょっときついと感じる程度の運動が効果的です。継続することが重要であり、無理のない運動計画を立てることで長期間の実践が可能になります。
骨密度を増加させる体重負荷運動には、ウォーキング、ジョギング、エアロビクス、階段の上り下りなどがあります。これらの運動は骨に体重の負荷を与えることで、骨をつくる細胞を活発にします。
1日30分程度のウォーキングを週2~3回以上実施することが効果的です。夏であれば暑さを避けて木陰で30分程度、冬であれば1時間程度の散歩により、運動効果とともに日光浴によるビタミンD生成効果も得られます。
水泳などの非体重負荷運動は筋力強化やバランス向上には有効ですが、骨密度増加効果は限定的です。そのため、骨粗鬆症予防には体重負荷運動を中心とした運動計画が適しています。
開眼片脚立ち(ダイナミック・フラミンゴ体操)は、フラミンゴのように片脚で立つ運動です。体重を片脚に乗せることで、両脚立ちの倍の負荷を骨にかけることができ、骨を強くする効果があります。バランス感覚が鍛えられるため、転倒予防にも効果的です。不安な方は壁やテーブルにつかまりながら実施しても構いません。
ふくらはぎとアキレス腱のストレッチでは、壁に手をついて体を支えながら行います。前に出した脚の膝を曲げて体重をかけ、後ろの脚のふくらはぎを伸ばし、その後膝を曲げてアキレス腱を伸ばします。片脚30~40秒ずつを左右交互に実施します。
背筋を伸ばすストレッチは、立位では壁から20~30cm離れて立ち、壁に沿って両手を上にのばします。座位では頭の後ろで手を組み、両肘を後ろに引いて胸を開きます。これらは猫背予防と脊椎の変形防止に効果があります。

イチロウの訪問介護では、骨粗鬆症の方の転倒予防と安全な生活支援を提供しています。移動介助、入浴介助、食事介助、着替えのお手伝いなどの身体介護に加え、掃除、洗濯、調理などの家事支援も行います。
通院の付き添いサービスにより、定期的な骨密度検査の受診をサポートします。診察内容の聞き取りや薬の受け取りなど、医療機関との連携を通じて継続的な治療をサポートしています。
24時間対応可能な体制により、骨折などの緊急時にも迅速に対応できます。東京23区での看護コースでは、バイタル測定や医療処置など医療行為にも対応可能で、より専門的なケアを提供しています。
骨粗鬆症は適切な知識と対策により予防可能な疾患です。高齢化が進む現代において、骨の健康を維持することは自立した生活を送るために不可欠です。カルシウムやビタミンDを含む食事、体重負荷運動、危険因子の管理を継続することで、骨密度の低下を防ぎ、骨折リスクを大幅に軽減できます。早期から骨粗鬆症予防に取り組むことで、将来の要介護状態を回避し、健康で活動的な生活を長く維持することができるでしょう。
ここでは、骨粗鬆症について多くの方が抱く疑問にお答えします。骨の健康に関する正しい知識を身につけることで、適切な予防対策を講じることができるでしょう。
骨粗鬆症は「沈黙の病気」と呼ばれ、初期には自覚症状がほとんどありません。背が縮んだ、背中や腰が曲がった、背中や腰の痛みで動きづらいなどの症状が現れた時は、すでに進行している可能性があります。40歳を過ぎたら定期的な骨密度検査を受けることが重要です。
はい、男性も骨粗鬆症になります。女性より発症率は低いものの、男性ホルモンやエストロゲンの低下、生活習慣病、薬剤の長期使用などが原因となります。男性も年齢とともにリスクが高まるため、予防対策が必要です。
カルシウムだけでは不十分です。ビタミンDがないとカルシウムの吸収率が低下し、ビタミンKは骨の形成に必要です。さらにタンパク質も骨の構成成分として重要です。バランスの良い食事と適度な運動、日光浴を組み合わせることで、効果的な予防が可能になります。
週2~3回、ちょっときついと感じる程度の体重負荷運動が効果的です。ウォーキングなら1日30分程度が目安で、夏は木陰で30分、冬は1時間程度の散歩により運動効果と日光浴効果が得られます。水泳は筋力向上には良いですが、骨密度増加効果は限定的です。
薬の服用期間は患者さんの状態や骨折リスクによって異なります。ビスホスホネート系薬剤は通常3~5年間の服用が基本ですが、骨折リスクが高い場合はより長期間必要になることがあります。定期的な骨密度検査で効果を確認し、医師と相談して治療方針を決定します。