
フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法
介護にまつわるお役立ちコラム
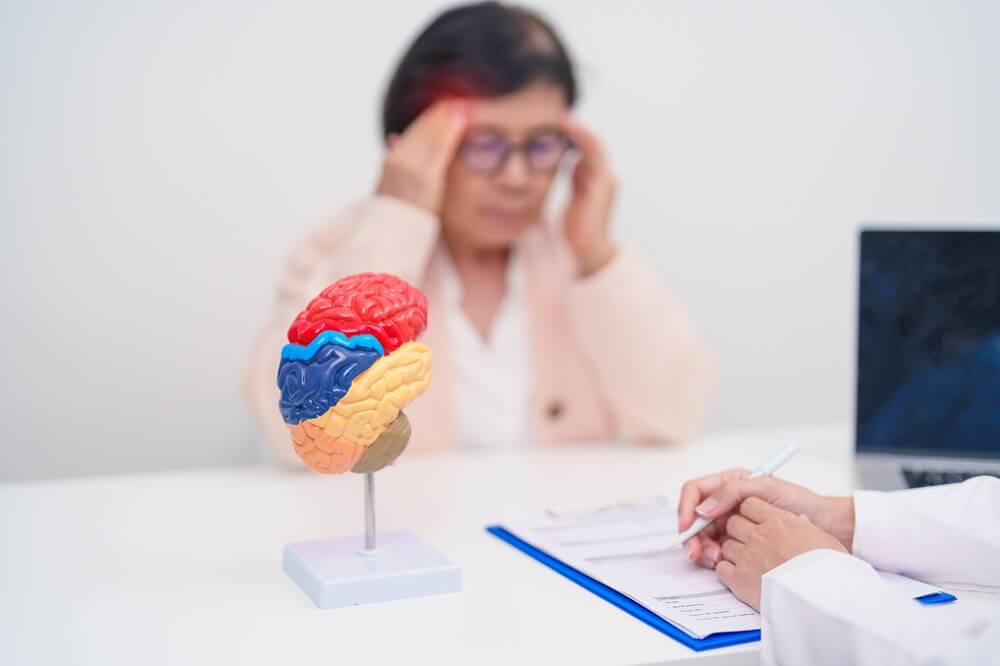
手足のふるえや動作の緩慢さなど、日常生活にじわじわと支障をきたす「パーキンソン病」。加齢に伴い発症リスクが高まるこの病気は、神経変性疾患のひとつであり、国内でも高齢化とともに患者数が増加しています。進行性ではあるものの、早期に兆候を察知し、適切な治療を行うことで、症状の緩和や生活の質の維持は十分に可能です。
本記事では、パーキンソン病の発症メカニズムや4大症状、進行過程に加え、非運動症状や診断方法、薬物療法から手術・リハビリまでを網羅的に解説。さらに、若年性パーキンソン病の特徴や支援制度についても触れています。パーキンソン病と向き合うための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

パーキンソン病は、脳の神経細胞が徐々に変性することで起こる運動障害の疾患です。主に手足の震えや筋肉のこわばり、動作の緩慢といった特徴的な症状が現れます。
この病気は高齢者に多く見られますが、若い世代でも発症する可能性があります。症状の進行は個人差がありますが、適切な治療により生活の質を維持することが可能です。
パーキンソン病では、大脳基底核の黒質と呼ばれる部位の神経細胞が変性します。大脳基底核の主要な神経伝達物質はドパミンです。ドパミンの主な作用は、運動調整や意欲の向上、快楽・多幸感の創出などです。
神経細胞が変性すると、ドパミンの生産量が減るとともに、大脳基底核の神経細胞同士をつなぐ接続の数が減少します。その結果、筋肉の動きを制御するという大脳基底核の正常な働きが損なわれて、振戦が起こるほか、動作が遅く小さくなり、姿勢や歩行に異常が現れます。
この病気の発症には、神経細胞の中にαシヌクレインというタンパク質が蓄積して、レビー小体と呼ばれるかたまりを形成することが関与していると考えられています。
参考:文部科学省|神経疾患の克服にむけた産官学連携の在り⽅について-パーキンソン病を例に
パーキンソン病とパーキンソン症候群は、症状が似ていますが原因や治療法が異なります。
| 項目 | パーキンソン病 | パーキンソン症候群 |
| 定義 | 黒質のドパミン神経細胞の変性による疾患 | パーキンソン病と同じ症状を他の原因で引き起こす状態 |
| 原因 | ドパミン神経細胞の変性とαシヌクレインの蓄積 | 多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、脳卒中、頭部外傷、薬剤など |
| 症状の特徴 | 運動症状が中心で左右差がある | 他の病気の症状(重度の血圧変化など)も伴うことが多い |
パーキンソン症候群の原因として以下が挙げられます。
パーキンソン病とパーキンソン症候群は治療法が違うため、専門医による正しい診断を受けることが重要です。
参考:日本赤十字社医療センター│パーキンソン病・パーキンソン症候群
パーキンソン病は一般的に50~79歳の間に発症します。現在、日本では約26万人の患者さんがおり、50代ごろから症状がみられ、年齢とともに患者さんが増加する傾向にあります。
40歳未満で発症することもあり、「若年性パーキンソン病」と呼ばれます。高齢になるほどパーキンソン病を発症する割合が増え、60歳以上では10万人に約1,000人と多くなっています。
患者数は10万人に100人~180人程度ですが、高齢化社会の進行に伴い、今後も患者数の増加が予想されます。早期発見と適切な治療開始により、長期にわたって良好な状態を保つことができるため、症状に気づいたら早めに専門医を受診することが大切です。
参考:厚生労働省│令和5年 患者調査 傷病分類編(傷病別年次推移表)

パーキンソン病の運動症状は、診断において最も重要な手がかりとなります。特徴的な症状として、静止時振戦、筋強剛、無動・寡動、姿勢反射障害の4つが挙げられ、これらは「4大症状」と呼ばれています。
運動症状は左右いずれか片方から始まることが多く、徐々に両側に広がる特徴があります。
| 症状名 | 特徴 |
| 振戦(しんせん) 安静時振戦 | 安静時に1秒間4~6回の頻度で起こる震え。丸薬丸め運動が特徴的 |
| 筋強剛(きんきょうごう) 筋固縮 | 筋肉のこわばりにより関節の動きに抵抗が生じる。歯車様強剛が典型的 |
| 無動・寡動(むどう・かどう) 動作緩慢 | 動作の開始困難、動きが小さく遅くなる。すくみ足や小字症が現れる |
| 姿勢反射障害(しせいはんしゃしょうがい) 姿勢保持障害 | バランス維持が困難となり転倒しやすくなる。病気の後期に出現 |
安静時振戦は、何もしないでじっとしているときに1秒間4~6回の頻度で起こる震えです。特徴的な症状として、小さな物体を転がすように手首と指を動かす「丸薬丸め運動」と呼ばれる手の動きが見られます。
睡眠中は震えが完全に止まりますが、精神的ストレスや疲労によって症状が悪化することがあります。通常は片方の手や足の震えから始まり、最終的にはもう一方の手、腕、脚にも広がっていきます。手を意図的に動かしているときには震えがあまり起こらないという特徴もあります。
筋強剛では、筋肉がこわばって関節の動きに抵抗が生じます。医師が患者の腕を動かそうとすると、特徴的な抵抗パターンが確認できます。
| 項目 | 歯車様強剛(歯車現象) | 鉛管現象(鉛管様強剛) |
| 抵抗の特徴 | 動き始めては止まり、止まっては動き始める断続的な抵抗 | 一定の連続的な抵抗 |
| 触診時の感覚 | 歯車のようなカクカクした感覚 | 鉛管を曲げるような一様な抵抗感 |
| 発生メカニズム | 振戦と筋強剛の合併 | 純粋な筋強剛 |
| パーキンソン病での頻度 | より一般的 | 比較的少ない |
顔面筋のこわばりにより、表情をコントロールする筋肉が正常に動かなくなり、顔の表情が乏しくなる「仮面様顔貌」が現れます。こわばりと可動性の低下により、筋肉痛と疲労が生じることもあります。
無動・寡動では、動作の開始が困難になり、動きが遅く小さくなります。
具体的な症状として以下が挙げられます。
歩行障害として「すくみ足」があり、足が地面にくっついたように感じて突然歩行が止まってしまいます。逆に「加速歩行」では、意図しないうちに次第に速足になり、転倒を避けようとしてつまずくような走り方になります。また、文字を書く際に字が小さくなる「小字症」も特徴的な症状です。
姿勢反射障害は、病気の後期(ヤール重症度分類Ⅲ度)に現れる症状です。体のバランスがとりにくくなり、軽く押されるだけでバランスを崩してしまいます。バランスを崩すと元に戻すことが困難で、そのまま転倒してしまうことがあります。
姿勢が前かがみになり、歩行中に止まったり方向転換をしたりすることが難しくなります。転倒リスクが高まるため、骨折の原因となる危険性があり、日常生活において十分な注意が必要です。症状が進行すると、首が下がったり体が斜めに傾いたりすることもあります。

パーキンソン病では、運動症状の他にもさまざまな非運動症状が見られます。非運動症状の中には運動症状の前に現れるものがあり、自律神経症状、精神症状、睡眠障害、感覚症状などが含まれます。
これらの症状は患者さんの生活の質に大きく影響するため、適切な理解と対処が重要です。
| 症状カテゴリー | 具体的な症状 | 頻度・特徴 |
| 自律神経症状 | 便秘 | 患者の8割程度にみられる最も多い症状 |
| 排尿障害 ・頻尿(特に夜間) ・尿失禁 ・排尿遅延(開始困難) | 排尿の開始と持続が困難、切迫した尿意 | |
| 起立性低血圧 ・立ちくらみ ・めまい ・失神 | 立ち上がったときの過度の急激な血圧降下 | |
| 発汗異常 ・過剰発汗 ・発汗低下 | 体温調節の異常 | |
| 性機能障害 | 自律神経の影響による機能低下 | |
| 精神症状 | うつ・不安 | 運動症状の何年も前から現れることがある |
| アパシー(無気力・無関心) | 身の回りのことへの関心の低下 | |
| 幻覚・妄想 ・幻視が最も多い ・被害妄想 | 認知症を発症した場合に特によくみられる | |
| 認知症 | 病気の後期に約3分の1の患者に現れる | |
| 睡眠障害 | 不眠症 ・中途覚醒 ・早朝覚醒 | 夜間の症状悪化や頻尿が原因 |
| レム睡眠行動障害 ・夢の内容に合わせた異常行動 ・大声での寝言 | 夢に合わせて体を動かし、隣で寝る人にけがをさせることもある | |
| 日中の過度の眠気 | 睡眠不足や薬剤の副作用による | |
| 感覚症状 | 嗅覚障害(嗅覚低下・脱失) | 初期からよくみられるが気づかれないことがある |
| 痛み・しびれ ・肩や腰の痛み ・手足の筋肉痛 ・異常感覚 | こわばりと可動性の低下により生じる | |
| その他 | 疲労感 | こわばりと可動性の低下により生じる |
| 体重減少 | 嚥下困難や食事摂取の制限による | |
| 脂漏性皮膚炎 ・頭皮や顔面の鱗屑 | 頭皮や顔面にしばしば鱗屑が生じる |
便秘は患者の8割程度にみられる最も多い症状です。腸が内容物を送る動きがゆっくりになるため発生し、運動不足やパーキンソン病の主要な治療薬であるレボドパによって悪化することがあります。
排尿障害では以下の症状が現れます。
起立性低血圧は、立ち上がったときに過度の急激な血圧降下が起こる症状で、立ちくらみやめまいを引き起こします。対処法として、立ち上がるときはゆっくりと動作することが大切です。
うつ症状は運動症状が発生する何年も前からみられることがあり、パーキンソン病の重症化とともに悪化する傾向があります。うつ症状は運動症状を悪化させることもあるため、適切な治療が重要です。
幻覚、妄想、パラノイアなどの精神症症状は、認知症を発症した場合に特によくみられます。そこにないものが見えたり聞こえたりする幻覚や、矛盾を示す明確な証拠があるにもかかわらず特定の信念に固執する妄想が現れます。疑い深くなり、他者から危害を加えられると思い込むパラノイアも見られます。
認知症は病気の後期に約3分の1の患者に現れ、いくつかの手順を踏む行動が計画できなくなる遂行機能障害や物忘れなどの症状を示します。
レム睡眠行動障害は、正常であればレム睡眠中に体が動くことはないはずですが、夢の内容に合わせて体を動かすため、レム睡眠中に腕や脚が突然乱暴に動く症状です。ときに隣で寝ている人にけがをさせることもあります。
不眠症の原因として、排尿回数の増加や夜間の症状悪化により寝返りが困難になることが挙げられます。また、中途覚醒や早朝覚醒により十分な睡眠が取れなくなります。
睡眠不足により、抑うつや思考障害、日中の眠気が悪化します。また、パーキンソン病の治療薬による副作用として日中の過度の眠気が現れることもあります。
嗅覚障害(嗅覚脱失)は初期からよくみられる症状ですが、気づかれないことがあります。においがしなくなることで食欲が低下し、栄養摂取に影響を与える可能性があります。
全身症状として以下が現れます。
感覚異常として、肩や腰の痛み、手足の筋肉痛やしびれなどが現れます。これらはこわばりと可動性の低下により筋肉痛と疲労が生じることが原因です。

パーキンソン病は、かすかな症状で始まり、何年もかけてゆっくりと進行する病気です。初期症状を早期に発見し、適切な治療を開始することで、発症から長い年数にわたってよい状態を保つことができます。
症状の現れ方や進行パターンには個人差がありますが、特徴的な傾向を理解することで、早期発見と適切な対処につなげることが可能です。
パーキンソン病の初期症状として最も現れやすいのは、振戦(手足の震え)と嗅覚の低下です。運動症状では、通常は安静な状態にした片方の手で起こる振戦から始まることが多くなっています。
家族が気づきやすい変化として、表情をコントロールする顔面筋が正常に動かないため、顔の表情が乏しくなる「仮面様顔貌」があります。また、話し方が単調で小声になることも特徴的な初期症状の一つです。
非運動症状では、腸の動きがゆっくりになることによる便秘が早期から現れることがあります。
パーキンソン病の重要な特徴として、症状の強さに左右で差があることが挙げられます。運動症状は左右いずれか片方に発症することが多く、徐々に両方に見られるようになる進行パターンを示します。
振戦は通常、安静な状態にした片方の手で起こり、最終的にはもう一方の手、腕、脚にも広がっていきます。この左右差は診断において重要な手がかりとなります。
初期は片側の軽い震えや動作のぎこちなさから始まり、徐々に筋肉のこわばりや動作の緩慢さが加わり、進行とともに反対側にも症状が現れます。
40歳未満で発症するパーキンソン病は「若年性パーキンソン病」と呼ばれます。まれに小児や青年が発症することもあり、通常の高齢発症のパーキンソン病とは異なる特徴を持っています。
若年性パーキンソン病では、遺伝的要因が関与する可能性が高くなります。パーキンソン病の人の約10~25%には、パーキンソン病の近親者がおり、パーキンソン病を引き起こすいくつかの遺伝子変異が特定されています。
ただし、患者さんのほとんどは孤発性であり、遺伝性を示しません。
パーキンソン病は個人差はありますが、何年もかけてゆっくりと進行する特徴があります。現在は効果的な治療薬があるため、発症から長い年数にわたり、よい状態を保つことができます。
進行段階は重症度分類(ヤール分類)で評価され、日常生活への影響も段階的に変化します。
| ヤール分類 | 症状の特徴 | 日常生活への影響 |
| Ⅰ度(初期) | 片側のみの軽い運動症状 | 日常生活にほぼ支障なし |
| Ⅱ度(軽症) | 両側に軽度の運動症状、軽度の歩行障害 | 日常生活に軽度の支障 |
| Ⅲ度(中等症) | 明らかな歩行障害、姿勢反射障害の出現 | 日常生活に中等度の支障、介助が必要な場面が増加 |
| Ⅳ度(重症) | 起立・歩行が困難、日常動作に著しい障害 | 介助なしでの生活が困難 |
| Ⅴ度(最重症) | 車椅子生活または寝たきり状態 | 全面的な介助が必要 |

パーキンソン病の診断は、主に問診と神経学的診察に基づいて行われます。特定の検査で確定診断できるものではないため、症状の特徴や経過を詳しく評価することが重要です。
必要に応じて画像検査を行い、他の疾患を除外しながら診断を進めていきます。早期に正確な診断を受けることで、適切な治療を開始できます。
問診では、症状の詳細について以下の項目が確認されます。
服用中の薬剤(市販薬や健康食品も含む)の確認も重要で、薬剤によるパーキンソニズムを除外するためです。受診時にはお薬手帳を持参することが必要になります。
身体診察では、診断の確定に役立てるため、特定の動作テストが行われます。指で自分の鼻に触れる指鼻試験では、パーキンソン病の患者が動作を行うと振戦が消失したり軽減したりします。
両手を膝に置いて裏返し元に戻すといった動作を素早く繰り返す検査では、パーキンソン病の患者は素早く動作を入れ替えることがうまくできません。歩行観察や姿勢反射の検査も実施されます。
診断がはっきりしない場合は、治療薬であるレボドパが投与され、明確な改善がみられれば診断の根拠となります。
CTやMRI検査は、パーキンソン病以外の脳の病気(脳血管障害や脳腫瘍など)の可能性を除外するために行われます。これらの検査により、構造的な脳の異常がないことを確認します。
MIBG心筋シンチグラフィーは、心臓の交感神経の状態を診る検査です。パーキンソン病の患者では、この薬剤が心臓への取り込みが低下することが知られており、診断の参考になります。
2014年からはドーパミントランスポーター(DAT)イメージングも利用可能となり、ドパミン神経の働きを可視化してパーキンソン病やレビー小体型認知症などを鑑別できます。
パーキンソン病の診断は、厚生労働省が作成した診断基準と照らし合わせて行われます。問診、神経学的診察、検査結果を総合的に判断し、基準を満たしていればパーキンソン病と診断されます。
パーキンソン病とパーキンソン症候群は治療法が異なるため、専門医による正しい鑑別診断を受けることが重要です。症状が似ていても原因が異なる疾患があるため、慎重な診断が必要になります。
早期に正確な診断を受けることで、適切な治療を開始でき、長期間にわたって良好な状態を保つことが可能になります。

パーキンソン病の治療は薬物療法が中心となります。診断がついた時から、多くの場合はお薬による治療が開始され、病状に合わせて薬剤の種類や量を調整していきます。
患者さんの年齢、症状の程度、副作用の有無などを総合的に判断して、最適な治療薬を選択することが重要です。
| 薬剤分類 | 代表的な薬剤名 | 作用機序 | 特徴・効果 | 主な副作用 |
| L-ドパ製剤 | レボドパ/カルビドパ | 脳内でドパミンに変換 | 治療効果が高く速効性に優れる | 吐き気、ジスキネジア、幻覚 |
| ドパミン受容体作動薬 | プラミペキソール、ロピニロール、ロチゴチン | ドパミン受容体を直接刺激 | 穏やかで安定した効果 | 眠気、衝動制御障害、幻覚 |
| MAO-B阻害薬 | ラサギリン、セレギリン | ドパミンの分解を抑制 | ドパミンの作用時間を延長 | 高血圧、錯乱 |
| COMT阻害薬 | エンタカポン、オピカポン | レボドパの分解を抑制 | レボドパの効果を延長 | 下痢、肝機能障害(トルカポン) |
| アデノシン受容体拮抗薬 | イストラデフィリン | アデノシンとドパミンのバランス調整 | 運動症状の改善 | 悪心、めまい |
| 抗コリン薬 | ベンツトロピン、トリヘキシフェニジル | アセチルコリンの作用を遮断 | 振戦に特に有効 | 口腔乾燥、錯乱、排尿困難 |
| ドパミン放出促進薬 | アマンタジン | ドパミン放出促進、回収抑制 | ジスキネジアの制御に有効 | 幻覚、むくみ |
| ドロキシドパ | ドロキシドパ | ノルアドレナリン補充 | 起立性低血圧の改善 | 高血圧、頭痛 |
レボドパはドパミン前駆体で、体内でドパミンに変換される薬剤です。この変換は脳の大脳基底核で起こり、パーキンソン病のために減少しているドパミンを補充します。
カルビドパを同時に投与することで、レボドパが大脳基底核に到達する前にドパミンに変換されるのを防ぎます。その結果、副作用が少なくなる上、脳でより多くのドパミンが利用できるようになります。
レボドパは筋肉のこわばりを軽減し、運動能力を改善し、しばしば振戦を大幅に軽減する高い治療効果と速効性を持つため、パーキンソン病治療の柱となっています。
ドパミン作動薬はドパミンに似た作用を持つ薬で、投与経路により特徴が異なります。
| 投与経路 | 薬剤名 | 特徴 | 利点 | 欠点・注意点 |
| 経口薬 | プラミペキソール | 1日3回服用 | 早期治療に適している | 単独では効果が数年で限定的 |
| ロピニロール | 1日3回服用 | レボドパとの併用可能 | 日中の眠気が一般的 | |
| 貼付薬 | ロチゴチン | 1日1回貼付 | 24時間安定した効果 | 皮膚刺激のリスク、貼る場所を毎日変更 |
| 注射薬 | アポモルヒネ | 即効性のレスキュー薬 | ウェアリング・オフに対応 | 1日5回まで、注射の技術が必要 |
| アポモルヒネ持続皮下注 (一部の国で利用可能) | ポンプによる持続投与 | 重度症状に対応 | 一部の国でのみ利用可能 |
MAO-B阻害薬やCOMT阻害薬はレボドパの補助薬として、ドパミンの分解を遅らせて作用時間を延長させます。アマンタジンは軽度の症状に単独で使用されるか、ジスキネジアの制御に特に有用です。
長期使用により現れる副作用には、幻覚(薬の種類や量の変更で改善)、むくみ(薬剤変更で対処)、ドパミン調節異常症候群(衝動的な買い物やギャンブル依存)などがあります。
これらの症状が現れた場合は、恥ずかしがらずに主治医に相談することが重要です。適切な薬剤調整により症状の改善が期待できます。
長期治療により現れる運動合併症には、ウェアリング・オフ現象とオン・オフ現象があります。
| 項目 | ウェアリング・オフ現象 | オン・オフ現象 |
| 定義 | 薬の効果時間が短くなる現象 | 薬の効果が突然現れたり消失する現象 |
| 発生時期 | レボドパ使用5年以上で半数以上に出現 | より進行した段階で出現 |
| 症状の変化パターン | 予測可能、次回服用前に症状出現 | 予測困難、突然の変化 |
| オン(効果あり)時 | 毎回の服用後に動ける時間が短縮 | 急に動けるようになる |
| オフ(効果なし)時 | 徐々に症状が現れる | 突然動けなくなる |
| 持続時間 | 徐々に短縮 | 数秒から数時間と変動 |
| 対処法 | 服用回数増加、徐放製剤への変更 | 薬剤追加や変更 |
| 生活への影響 | ある程度予測可能 | 日常生活の計画が困難 |
対処法として、1回の用量を減らして服用回数を増やす、レボドパの徐放製剤に切り替える、ドパミン作動薬やアマンタジンを追加するなどがあります。ジスキネジアには薬の量や種類の調整が効果的です。

パーキンソン病治療では、薬物療法が中心となりますが、薬剤だけでは十分な効果が得られない場合や副作用が問題となる場合には、手術療法が選択されることがあります。
また、診断後すぐにリハビリテーションを開始することで、症状の進行を抑制し、生活の質を向上させることができます。日常生活の工夫と合わせて総合的なアプローチが重要です。
脳深部刺激療法は、大脳基底核の一部に微小な電極を手術で埋め込み、振戦を引き起こしている特定の領域に微弱な電気を送る治療法です。
適応条件として以下が挙げられます。
この部分を刺激することにより、不随意運動と振戦が大幅に減り、オン・オフ現象のオフ部分の時間が短くなります。脳深部刺激療法は専門施設でのみ行われており、薬物療法を補完する有効な治療選択肢となっています。
パーキンソン病と診断されたら、すぐにリハビリテーションを始めることが大切です。有酸素運動やストレッチなどを積極的に行うことで、生活に支障のない状態を長く保つことが可能です。また、薬物療法と並行してリハビリを行うことで、機能の維持が期待できます。
理学療法士や作業療法士から、筋緊張を改善して関節の可動域を維持するための体操について助言を受けることができます。また、自立を維持するための歩行器などの補助器具の使用方法についても指導を受けられます。
定期的な運動プログラムを守ることで、症状の進行を抑制し、日常生活動作の維持が可能になります。
日常生活を安全で快適に送るための環境整備が重要です。転倒予防のための対策として以下が有効です。
日常動作を楽にする工夫として、服のボタンを面ファスナーに替える、面ファスナー付きの靴を買うなどがあります。ジッパータブ(ファスナーを引くための補助器具)やボタンエイド(ボタンをかけるための補助器具)を使用することも効果的です。
できるだけ多くの日常活動を続けることで、機能の維持と生活の質の向上が図れます。
パーキンソン病になると、口の周りの動きの影響で、「声が小さくなる」「早口になる」「声がかすれる」などの障害が現れることがあります。これらの症状にもリハビリテーションが有効です。
具体的な訓練方法として、本や新聞を大きな声で読む、カラオケで大きな声で歌うなどがあります。これらの練習により発声機能の維持・改善が期待できます。
食道が内容物を送る動きがゆっくりになるため、嚥下困難をきたすことがあります。その結果、口腔分泌物や食べたものを肺に吸い込む誤嚥が生じる可能性があり、誤嚥により肺炎が起こることがあるため、適切な嚥下訓練が重要です。

パーキンソン病と共に生きるためには、医療機関での治療だけでなく、日常生活を支える幅広い支援が必要です。介護保険制度だけでは対応できない細やかなニーズに対応するため、民間の訪問介護サービスの活用が重要な選択肢となります。
イチロウの訪問介護・看護サービスは、介護保険外で24時間対応が可能な専門サービスです。あらゆるご要望に対してヘルパー手配率96%を実現し、介護保険では対応できない介護・生活支援を一流の介護士がサポートします。夜間帯もすべてのサービスに対応し、パーキンソン病の症状が悪化しやすい時間帯でも安心してご利用いただけます。
看護コースでは医療行為にも対応しており、たん吸引や経管栄養などの医療処置、終末期ケア・緩和ケアまで専門看護師が提供します。
パーキンソン病に対する正しい理解と早期対応は、患者とその家族の生活の質を大きく左右します。症状や診断方法、治療選択肢を理解することで、適切な医療機関を受診し、最適な治療方針を選択できるようになります。薬物療法、手術療法、リハビリテーションを組み合わせた包括的なアプローチにより、症状の進行を抑制し、長期間にわたって良好な状態を維持することが可能です。パーキンソン病について学ぶことで、病気への不安を軽減し、希望を持って治療に取り組むことができるでしょう。
パーキンソン病について患者さんやご家族から寄せられる代表的な疑問にお答えします。病気への理解を深め、適切な治療や日常生活の管理に役立てていただくため、わかりやすく解説します。
初期症状として、安静時の手足の震え、動作の遅さ、筋肉のこわばり、嗅覚の低下が挙げられます。また、表情が乏しくなる「仮面様顔貌」や声が小さくなる、便秘などの症状も現れることがあります。これらの症状に気づいたら、早めに神経内科を受診することが大切です。
パーキンソン病患者の約10~25%に家族歴がありますが、患者さんのほとんどは孤発性で遺伝性を示しません。若年性パーキンソン病では遺伝的要因が関与する可能性が高くなりますが、40歳未満での発症は稀です。家族歴がある場合でも、必ず発症するわけではありません。
レボドパを5年以上服用すると、ウェアリング・オフ現象やオン・オフ現象が現れることがあります。これは薬の効果時間が短くなったり、効果が突然現れたり消失したりする現象です。服用回数の調整や徐放製剤への変更、他の薬剤の追加により改善が期待できます。
脳深部刺激療法(DBS)は、病気が進行し認知症や精神症状がなく、薬剤の効果が不十分または重い副作用がある場合に検討されます。大脳基底核に電極を埋め込み微弱な電気刺激を送ることで、振戦や不随意運動を大幅に軽減し、オフ時間を短縮する効果があります。