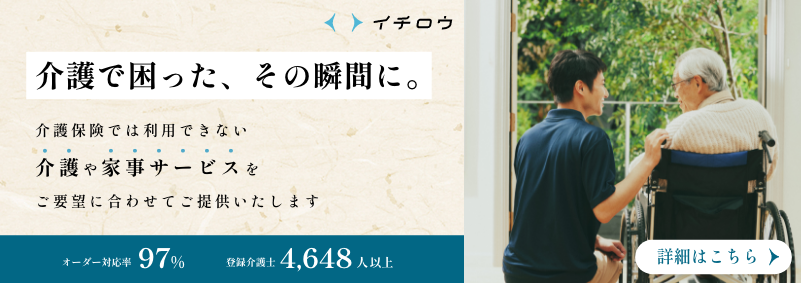フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法
介護にまつわるお役立ちコラム

歩行に不安を感じる高齢者や身体機能が低下した方にとって、歩行器は安全な移動と自立をサポートする重要な福祉用具です。しかし、「どんな種類があるの?」「どう選べばいいの?」と悩まれる方も多いでしょう。
本記事では、歩行器の種類と選び方、正しい使用方法、介護保険でのレンタル方法までを詳しく解説します。ご自身にぴったりの歩行器を見つけて行動範囲を広げ、より豊かな生活を送るための参考にしてください。

歩行器は、高齢者や身体機能が低下した方の歩行をサポートする福祉用具です。四点で地面を支える構造により、安定性が高く、転倒リスクを軽減します。
両手でハンドルを握り、体重を支えながら移動することで、足腰への負担を和らげる効果があります。杖では歩行が不安定な方でも、歩行器があれば安全に移動できるようになります。そのため、自立した生活を送るために欠かせない重要な福祉用具です。
以下では、歩行器の具体的な役割やメリット、必要となる状況について解説します。
歩行器の主な役割は、利用者の体重を両腕で支えることで下肢にかかる負担を軽減し、安定した歩行をサポートすることです。四点で地面を支える構造により、杖よりも広い支持基底面を確保でき、バランスを崩しにくくなります。
これにより転倒リスクが大幅に減少し、歩行に対する不安感も軽減されるでしょう。歩行器の使用によって行動範囲が拡大し、自分で移動する喜びを取り戻せる点は、心理的にも大きなメリットといえます。結果として、生活の質が向上し、健康維持にもつながります。
加齢による筋力低下や疾患によってバランス機能が低下した方、関節痛などで歩行に痛みを伴う方に歩行器は効果的です。具体的には、以下のような方が対象です。
また、手術後のリハビリ期間中など、一時的に歩行能力が低下している状況でも活用できます。自立歩行は可能だが長距離の移動に不安がある場合も、歩行器によって行動範囲を広げることが可能です。
歩行器とシルバーカーは外見が似ていますが、構造と用途に大きな違いがあります。歩行器はコの字型のハンドルが特徴で、体重をかけて使用することを前提に設計されています。
一方、シルバーカーは直線的なハンドル形状で、体重をかけるつくりにはなっていません。主に荷物を収納したり、腰を掛けて一時的に休憩したりするための道具です。さらに大きな違いとして、歩行器は介護保険の福祉用具貸与の対象となりますが、シルバーカーは対象外です。

歩行器には高齢者や身体機能が低下した方の状態に合わせて選べる複数のタイプがあります。
大きく分けると下記の3種類に分類され、それぞれ構造や使い方、向いている方が異なります。
以降では、各タイプの特徴や適している方について解説していきます。
ご自身や介護されるご家族に最適な歩行器を選ぶ参考にしてください。
固定型歩行器は、最もスタンダードで安定性に優れたタイプです。身体の前面と側面をコの字型のフレームで囲む構造になっており、両手でハンドグリップを握って体重を支えます。使用時は歩行器全体を持ち上げて前方に置き、そこに体重をかけて一歩進むという動作を繰り返します。
軽量で持ち上げやすく、階段の昇降も可能ですが、移動速度は比較的遅いため主に屋内での使用に適しています。収納に便利な折りたたみ機能や高さ調整機能がついた製品もあるでしょう。上半身にある程度筋力がある方や、脚に痛みがあり筋力が弱い方、杖では不安定になる方におすすめです。
交互型歩行器は固定型に似た構造ですが、左右のフレームをそれぞれ個別に動かすことができる点が大きな特徴です。歩行時には手を振るような感覚で左右のフレームを前方へ交互に動かしながら進みます。この方法により、固定型よりも自然な歩行リズムで移動することが可能になります。
使用には固定型より高いバランス機能が求められますが、常に左右どちらかの足が地面に接しているため安定性は高く保たれています。この歩行器は、片足に痛みがある方や、姿勢バランスが取りにくく歩行が困難な方に特に適しています。また、固定型よりもやや速いペースで歩けるため、行動範囲を広げたい方にも向いているでしょう。
キャスター付き歩行器は、フレームの下部にキャスターや車輪がついており、持ち上げずに押しながら歩けるタイプです。両手で支えながら歩くタイプと、肘など両腕で体重を支えられるタイプがあります。多くの製品にはハンドブレーキや腰掛け、買い物に便利な荷物入れなどの機能が備わっています。
さらに高機能なものには、モーターや傾斜センサー、折りたたみ機能、高さや幅の調整機能、安全なブレーキシステムなどが搭載されているものもあるでしょう。足腰に痛みのある方や筋力の弱い方、リハビリをはじめたばかりの方に向いています。屋外での使用も可能なため、行動範囲を広げたい方にも最適な選択肢といえるでしょう。
ただし、車輪の大きさによっては段差を超えにくい場合があるため、選ぶ際は専門家に相談するようにしましょう。

ひとくくりに歩行器といっても、その種類は豊富です。ご自身の身体状況に合ったものを選択しなければ、症状悪化や転倒リスクの可能性があります。
ここでは歩行器の選び方について紹介しますが、実際に購入やレンタルする場合は専門家に相談してから決めることをおすすめします。
高齢者が歩行器を選ぶ際は、自身の筋力やバランス機能を把握し、それに合った種類・形状の歩行器を選ぶことが大切です。歩行器にはさまざまな種類があり、それぞれ必要とされる身体能力や特徴が異なるからです。
以下に、筋力やバランスを考慮した歩行器の選び方を示します。
筋力や身体バランスはご自身で判断するのが難しいため、専門家に相談してから決めるようにしましょう。「近くに専門家がいない」という方は、担当のケアマネジャーや役所の介護福祉課に相談してみてください。福祉用具の専門家を紹介してくれるでしょう。
歩行器は、使用する環境(室内/屋外、段差の有無、坂道など)や目的(通院、買い物、家事など)に応じた選び方をするのも重要です。
具体的な環境と、それに適した歩行器タイプは、以下のとおりです。
【環境別の歩行器選択例】
| 使用環境 | 適した歩行器タイプ | 選択理由 |
| 屋内(バリアフリー) | どのタイプでも使用可能 | 段差がなく安全に使用できるため |
| 屋内(段差あり) | 固定型歩行器、交互型歩行器 | 持ち上げて段差を越えることができるため |
| 病院や施設の広い環境 | サークル型歩行車 | 広いスペースで安定して移動できるため |
| 屋外(短距離) | 固定型歩行器、交互型歩行器 | 短距離であれば屋外でも使用可能 |
| 屋外(長距離) | 四輪歩行車、シルバーカー | 安定性があり長距離の移動に適している |
| 坂道のある環境 | 電動アシスト付きの四輪歩行車 | 坂道でも安全に使用できるため |
【目的別の歩行器選択例】
| 使用目的 | 適した歩行器タイプ | 選択理由 |
| 通院・買い物 | 折りたたみ可能な歩行器 | バスなどの乗り物利用時に便利 |
| 食事や食器の運搬 | トレイ付きの四輪歩行車 | 食器や食事などの荷物を運ぶことができる |
| リハビリ訓練 | キャスター付き歩行器、サークル型歩行車 | リハビリをはじめたばかりの方に適している |
| 室内での家事 | トレイつきの歩行器 | 家事をしながら移動することができる |
| 長時間の歩行や外出 | 腰かけ付きの四輪歩行車 | 疲れたときに休憩できるため |
| 買い物などで荷物が必要な場合 | 荷物入れ付きの歩行車 | 買い物した荷物を収納できるため |
上記はあくまで一般的な目安です。選ぶ際は、ご自身の身体状況と照らし合わせながら選択するようにしましょう。

歩行器は身体状態にあわせて適切なものを選ばないと、症状が悪化するなどの逆効果を招くケースがあります。不適切な歩行器の使用は転倒などの事故につながる危険性もあるため、十分な注意が必要です。選択の際には、ご自身の判断だけでなく、福祉用具専門相談員やケアマネジャー、場合によっては理学療法士や医師など、専門家の意見を参考にすることが重要です。
専門家は身体状態を適切に評価し、安全で効果的な歩行器を提案してくれるでしょう。また、定期的な再評価を行うことで、身体状態の変化に合わせた調整や機種変更も可能になります。
歩行器選びでは、全身の筋力状態を総合的に判断する必要があります。上半身の筋力が十分にある方なら、持ち上げ式の固定型歩行器も問題なく使用できますが、腕力に不安がある場合はキャスター付きの押して使うタイプが適しています。
下肢の状態も重要で、両脚に痛みや筋力低下がある場合は安定性の高い固定型が、片側だけに症状がある場合は交互型が適切かもしれません。また、左右のバランス感覚も考慮点の一つです。バランスが著しく悪い方には四点接地の安定した歩行器が必要になるでしょう。
体力面では、長距離移動が必要な方には腰掛け機能付きの歩行車が役立ちます。全体的な歩行レベルに合わせて、無理のない支持力を持つタイプを選ぶことが大切です。
歩行器は使用する環境や目的によっても選び方が変わります。段差のないバリアフリーの室内環境であれば、どのタイプも使用可能ですが、段差がある場所では持ち上げられる固定型や交互型が適しています。
屋外での使用を考えるなら、四輪歩行車やキャスター付き歩行器が安定性と操作性に優れているでしょう。特に坂道が多い環境では、ブレーキ機能が充実した製品や電動アシスト付きの歩行車が安全です。
目的別には、バスなどの公共交通機関を利用した通院には折りたたみ式の製品が便利です。買い物には荷物入れ付きの歩行車が重宝します。家事をしながらの移動にはトレイ付きのタイプが食器や食事を運ぶのに役立ちます。長時間の外出予定がある場合は、疲れた時に休憩できる腰掛け機能付きの歩行車が適しているでしょう。
リハビリ初期の方には、肘を支えるタイプのサークル型歩行車が体重支持の面で安心です。このように、日常生活での具体的な使用シーンを想定して選ぶことが、歩行器を最大限に活用するポイントとなります。

歩行器は介護保険でレンタルできる福祉用具の一つです。適切な歩行器を選ぶことで、高齢者や身体機能が低下した方の行動範囲が広がり、自立した生活を送るサポートとなります。介護保険を利用すれば、費用負担を抑えながら専門家のアドバイスのもと、最適な歩行器を利用することができます。
以下では、介護保険での歩行器レンタルの条件や手続き、メリットについて解説します。
歩行器は、介護保険の福祉用具貸与サービスの対象となっています。このサービスを利用できるのは、要支援1・2、要介護1~5の認定を受けた方です。レンタルできるのは市区町村(または都道府県)の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」からのみで、専門知識を持った福祉用具専門相談員が身体状態や生活環境に合った用具選びをサポートします。
レンタル費用の目安は、自己負担1割の場合で月額数百円程度となっています。ただし、収入状況によっては2~3割負担になることもあり、また市区町村や事業者によって若干の価格差が生じることもあるでしょう。
参考:厚生労働省「どんなサービスがあるの? - 福祉用具貸与」
歩行器などの福祉用具は、身体状態に合ったものを使用することが重要です。レンタルの場合、福祉用具専門相談員が定期的に自宅を訪問し、メンテナンスや状態確認を行います。身体状態の変化に応じて、ベストな歩行器に選び直すこともできるため、常に最適な状態で使用できる点が大きなメリットです。
さらに、アフターサービス費用が無料であることや、1か月単位での更新で利用終了時には引き取りも行われるので、試しに使いたい方にも安心です。購入に比べて長期的な費用対効果も高く、専門家のサポートが継続的に受けられることから、レンタルがおすすめといえるでしょう。
歩行器の選定には専門家のサポートを活用することが重要です。まず相談窓口として、ケアマネジャーや地域包括支援センターが挙げられます。ケアマネジャーは介護保険サービスの調整役として、適切な福祉用具専門相談員を紹介してくれるでしょう。福祉用具専門相談員は実際の使用環境を確認し、身体状態に合った歩行器を提案します。
また、身体状況によっては、福祉用具専門相談員やケアマネジャーだけでなく、主治医や看護師、理学療法士などの医療専門職のアドバイスも受けることをおすすめします。複数の専門家の視点を取り入れることで、より安全で効果的な歩行器選びが可能になります。

歩行器を使用されている方にとって、外出時の付き添いは大きな安心につながります。イチロウでは介護保険の制限に縛られない柔軟なサービスとして、通院や買い物、お散歩などの外出付き添いを提供しています。歩行に不安がある方も、経験豊富な介護士がそばに寄り添うことで安全に外出を楽しめるでしょう。
イチロウの特徴は「やってほしい」を叶えるオーダーメイド型のサポートです。利用者一人ひとりの状態や希望に合わせた丁寧な介助を心がけており、歩行器の操作補助から段差の移動まで細やかなサポートが可能です。
要介護度に関わらず、また認定前の方でも利用できるため、歩行器を使い始めたばかりで不安がある方も安心してご相談いただけます。外出先での移動介助だけでなく、自宅から外出先までの送迎も含めた一貫したサービスを提供しています。
歩行器は高齢者や身体機能が低下した方の自立した生活をサポートする重要な福祉用具です。固定型、交互型、キャスター付きの3タイプがあり、それぞれ身体状態に合わせて選ぶことが大切です。適切な歩行器選びには筋力や身体バランス、使用環境や目的の検討が欠かせません。
介護保険を利用して要支援1から要介護5までの方はレンタルが可能で、専門家のサポートを受けながら最適な歩行器を選定できます。最近ではスタイリッシュなデザインの製品も増えており、見た目を気にする方も選択肢が広がっています。歩行器の利用によって行動範囲が広がり、痛みの軽減や転倒予防など、生活の質向上も期待できるでしょう。