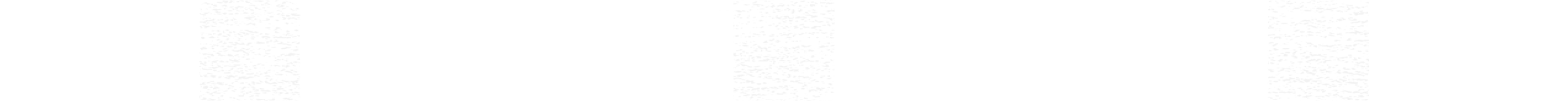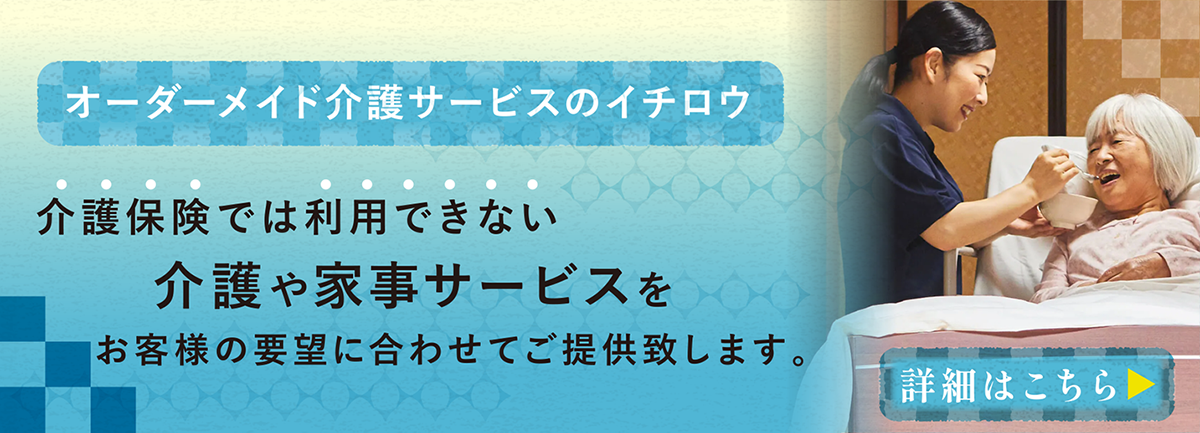介護にまつわるお役立ちコラム
介護と仕事を両立はできる?両立支援や介護保険サービスなどのポイントを解説

「親の介護が始まったけど、仕事を辞めなければならないのだろうか?」そんな不安を抱える方も多いのではないでしょうか。実は、介護と仕事の両立は決して不可能ではありません。適切な支援制度や介護サービスを活用すれば、キャリアを諦めずに介護に取り組めます。
本記事では、両立を実現するためのポイントや利用できる制度について詳しく解説します。介護に直面した際の不安を軽減し、仕事と介護を上手く両立させるためのヒントが見つかるはずです。介護離職を考える前に、ぜひ参考にしてみてください。
1介護と仕事の両立はできるのか

介護と仕事の両立は可能ですが、多くの方にとって大変な挑戦となります。なぜ大変なのでしょうか。主に以下の理由が挙げられます。
- 時間的制約:介護には予測不可能な緊急事態が発生することがあり、仕事との両立が難しくなることがあります。
- 身体的・精神的負担:介護は身体的にも精神的にも負担が大きく、仕事との両立によりさらにストレスが増加する可能性があります。
- 経済的負担:介護にかかる費用と、仕事の時間が減ることによる収入減少のバランスを取ることが難しい場合があります。
- キャリアへの影響:介護のために仕事の時間を減らしたり、責任ある立場を辞退せざるを得ない場合があります。
- 情報不足:利用可能な支援サービスや制度について十分な情報を得られないことがあります。
介護と仕事を両立している人の割合
令和4年就業構造基本調査によると、介護をしている有業者は365万人で、これは全有業者の5.4%にあたります。また、介護をしている人のうち、58.0%が有業者となっています。
今後、この割合は増加していくと推測されます。その理由として以下が挙げられます。
- 高齢化社会の進行:日本の高齢化率は上昇を続けており、介護を必要とする人の数が増加しています。
- 介護保険制度の充実:在宅介護サービスの拡充により、仕事と介護の両立がしやすくなっています。
- 企業の取り組み:介護休業制度や短時間勤務制度など、仕事と介護の両立を支援する制度が整備されつつあります。
- 政府の施策:「介護離職ゼロ」を目指す政策により、両立支援の環境が整備されつつあります。
- 経済的必要性:年金制度の変更や長寿化により、働き続ける必要性が高まっています。
参考:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」
介護離職者の割合
令和4年就業構造基本調査によると、過去5年間に介護・看護のために前職を離職した人は47.4万人となっています。これは、前職のある無業者の6.3%に相当します。
介護離職の主な理由には以下が挙げられます。
- 仕事と介護の両立が困難
- 介護サービスの利用に関する情報不足
- 職場の理解不足
- 経済的理由(介護費用の負担)
- 心身の疲労
介護離職によって起こりうる問題には以下があります。
- 収入の減少による経済的困難
- キャリアの中断によるスキルの低下
- 社会からの孤立
- 将来の年金受給額の減少
- 再就職の困難
介護離職は可能な限り避けることが望ましいですが、状況によっては避けられない場合もあります。重要なのは、離職する前に利用可能な支援制度や代替案を十分に検討することです。また、一時的な離職であっても、将来の再就職を見据えてスキルの維持や情報収集を行うことが重要です。
参考:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」
2介護離職は極力避けた方が良い理由

介護と仕事の両立は確かに大変で、身体的にも精神的にも大きな負担がかかります。しかし、そうした困難があるにもかかわらず、可能な限り介護離職は避けることをお勧めします。その理由は以下のとおりです。
- 収入がなくなる
介護離職により収入が途絶えると、生活の維持が困難になるだけでなく、将来の年金にも影響を及ぼします。また、介護にかかる費用を捻出することも難しくなり、長期的な経済的安定が損なわれる可能性があります。
- 再就職が難しくなる
一度退職すると、再就職が困難になる可能性が高くなります。特に、長期間仕事から離れると、スキルの陳腐化や経験不足により、希望する職種や待遇での再就職が難しくなることがあります。
- 社会との繋がりが断たれ、メンタルが不安定になる
仕事を通じた社会とのつながりが失われることで、孤立感を感じたり、自己肯定感が低下したりする可能性があります。介護者自身のメンタルヘルスに悪影響を及ぼし、ひいては介護の質にも影響を与える可能性があります。
- 介護の質への影響
仕事を続けることで、介護に対する新しい視点や情報を得られることがあります。また、仕事と介護のバランスを取ることで、効率的な時間管理や問題解決能力が向上し、結果として介護の質が向上する可能性もあります。
- 将来的な不安
介護が終了した後の生活設計が難しくなります。特に、長期間仕事から離れていると、その後の人生設計に大きな影響を与える可能性があります。
介護と仕事の両立は確かに困難を伴いますが、可能な限り両立を目指すことが望ましいと言えます。そのためには、利用可能な介護サービスや職場の支援制度を最大限に活用し、周囲のサポートを得ながら、自身の健康管理にも気を配ることが重要です。
3仕事と介護を両立するための7つのポイント

仕事と介護を両立させるためには、以下の7つのポイントが重要です。
- 普段から勤務先や家族に状況を話しておく
- 仕事と介護の両立支援制度を利用する
- 介護保険サービスを利用する
- 要介護認定前から調整を行う
- 小さなことでもケアマネージャーに相談する
- 自分の時間も確保する
- 家族や近隣住民と良好な関係性を築いておく
それぞれについて説明します。
仕事と介護の両立支援制度を利用する
両立支援制度とは、従業員が仕事と介護を両立できるよう、企業が提供する様々な制度やサポートのことです。主な両立支援制度には以下のようなものがあります。
■両立支援制度例
| 制度名 | 概要 |
| 介護休業 | 介護休業は、労働者が要介護状態の家族を介護するために、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して休業を取得できる制度です。 |
| 介護休暇 | 介護休暇は、要介護状態の家族の介護や通院の付き添いなどのために、年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで取得できる制度です。時間単位での取得も可能です。 |
| 所定労働時間の 短縮等の措置 | 所定労働時間の短縮やフレックスタイム制度、時差出勤制度などを活用することで、介護に合わせた柔軟な働き方が可能になります。 |
| 所定外労働の制限 | 介護が終了するまで、所定外労働の免除を請求できる制度です。 |
| 時間外労働の制限 | 1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限できる制度です。 |
| 深夜業の制限 | 午後10時から午前5時までの深夜労働を制限できる制度です。 |
| 転勤に対する配慮 | 介護が必要な場合、転勤を配慮する制度です。 |
| 介護休業給付金 | 介護休業中に給与の67%を受給できる介護休業給付金があります。 |
これらの支援制度は、原則として要介護状態の対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)が利用できます。ただし、勤務先の労使協定によっては取得できない場合もあります。
会社から制度の利用について、不当な扱いを受けた場合は、各都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)や労働基準監督署に相談することができます。
介護保険サービスを利用する
介護保険サービスとは、介護を必要とする高齢者やその家族を支援するために、公的な保険制度に基づいて提供されるサービスです。
例えば、訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)などのサービスを受けられます。
これらのサービスを利用することで、介護の負担を軽減し、仕事との両立をより容易にできます。
| 指定・監督 | サービス名 | 概要 |
| 都道府県 | 居宅サービス | 訪問介護や訪問看護、福祉用具貸与などのサービスを自宅で受けられます。 |
| 施設サービス | 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入所してサービスを受けられます。 | |
| 居宅介護支援 | ケアマネージャーによる介護計画の作成や相談支援を受けられます。 | |
| 介護予防サービス | 介護予防のためのリハビリテーションや健康管理サービスを利用できます。 | |
| 市町村 | 地域密着型サービス | 地域の特性に応じた小規模な介護サービスを利用できます。 |
| 地域密着型介護予防サービス | 要支援者向けの地域密着型サービスを利用できます。 | |
| 介護予防支援 | 要支援者向けのケアプラン作成や相談支援を利用できます。 |
要介護度によって利用できるサービスが異なります。例えば、要支援1・2の方は介護予防サービスを、要介護1〜5の方は介護サービスを利用できます。
介護保険サービスの自己負担割合は、原則として費用の1〜3割です。ただし、所得に応じて負担割合が変わります。
関連記事:「介護保険サービスの種類一覧|サービス内容と利用の流れを解説(KWD:介護保険サービス)」に内部リンク
要介護認定前から調整を行う
要介護認定前から調整を行うことは、スムーズな介護開始と仕事との両立のために重要です。介護保険の利用申請から要介護認定されるまでには通常1〜2ヶ月かかります。早めに準備を始めることで、認定後すぐにサービスを利用できる体制を整えられるでしょう。
小さなことでもケアマネージャーに相談する
ケアマネージャーは介護サービスの専門家であり、様々な情報提供や助言をしてくれます。小さな疑問や悩みでも相談することで、介護の質を向上させ、仕事との両立をより効果的に進められます。相談は電話やメール、直接面談など様々な方法で行えます。
自分の時間も確保する
自分の時間を確保することは、介護者自身の心身の健康を保つために非常に重要です。自分の時間を持つことで、ストレス解消やリフレッシュができ、結果として介護の質も向上します。自分の時間を確保しないと、燃え尽き症候群に陥る恐れがあります。
家族や近隣住民と良好な関係性を築いておく
家族や近隣住民との良好な関係は、緊急時のサポートや日常的な助け合いにつながります。仕事と介護の両立がより容易になるでしょう。良好な関係性を築くには、日頃からコミュニケーションを取り、互いに助け合う姿勢を示すことが大切です。
4保険適用外サービスの利用も調べておく

介護と仕事の両立を考える上で、介護休業などの両立支援制度は重要な役割を果たしますが、これらの制度には期限があることが多いのが現実です。一方で、介護は長期にわたり、終わりが見えないことが多いのが特徴です。そのため、多くの人は介護保険サービスを利用しつつ、一定期間後は仕事と介護の両立を図ることになります。
しかし、介護保険サービスにも限界があります。特に以下のような点で課題が生じることがあります。
- 長時間利用が難しい
- 早朝・夜間の利用が制限される
- 当日の支援時間の変更が困難
これらの課題を補完し、より柔軟な介護支援を受けるために、保険適用外サービスの利用を検討する必要が出てきます。そこで注目されているのが、イチロウのようなプライベートヘルパーサービスです。
【イチロウのサービスの特徴・メリット】
- 柔軟な時間設定:24時間365日対応可能で、長時間や早朝・夜間の利用も可能です。
- オーダーメイドのサービス:介護保険制度の制限にとらわれず、利用者のニーズに合わせたサービスを提供します。
- 迅速な対応:最短で当日からのサービス利用が可能です。
- 高品質なサービス:厳しい基準で選ばれた介護士が、ホスピタリティの高いサービスを提供します。
- 幅広いサービス内容:自宅での介護や家事支援から、通院の付き添い、入院中の介護まで対応可能です。
- 透明性の高いサービス:オンラインレポートによりサービス内容を確認できます。
【イチロウのようなサービスが特に有効な方】
- 仕事の都合で不規則な時間帯に介護支援が必要な方
- 介護保険サービスでは対応できない細かなニーズがある方
- 急な介護ニーズに対応する必要がある方
- 長時間の介護支援が必要な方
- 介護と仕事の両立に悩む方
- 介護認定前でも早急に支援が必要な方
保険適用外サービスは、介護保険サービスを補完し、より柔軟で充実した介護支援を受けることができます。ただし、費用が全額自己負担となるため、予算と相談しながら、介護保険サービスと組み合わせて利用することをおすすめします。
仕事と介護の両立は決して容易ではありませんが、両立支援制度、介護保険サービス、そして保険適用外サービスを上手に組み合わせることで、より良いバランスを見つけることができるでしょう。
5現職と介護の両立がきつい場合は、転職も視野に入れよう

介護と仕事の両立が難しい理由として、介護は予測が難しく、突発的な対応が求められることが挙げられます。また、介護を行う人は働き盛りの世代が多く、企業の中核を担う労働者であるため、職責の重い仕事と介護の両立が難しくなることが多いです。
介護と仕事の両立が困難な場合、介護と両立しやすい仕事や職場に転職することも一つの手段です。以下に具体的な仕事や働き方を紹介します。
- 派遣社員
派遣社員は、勤務時間やシフトが比較的柔軟で、介護と仕事を両立しやすい働き方です。シフトを自分の都合に合わせて提出できるため、介護の時間を確保しやすいのが特徴です。また、パートやアルバイトよりも時給が高いことが多く、効率的に収入を得られる点も魅力です。
- 在宅ワーク
在宅ワークは、介護との両立に非常に有効です。自宅で仕事ができるため、食事の用意や介助、洗濯などの介護に柔軟に対応できます。また、通勤が不要なため、体力を温存できる点もメリットです。特別なスキルがある場合は、フリーランスや在宅ワーカーとして働くことも検討できます。
- リモートワーク可能な仕事
リモートワーク可能な仕事であれば、場所を選ばずに働けるため、介護のために離職する必要がありません。実家と勤務先が離れている場合でも、リモートワークなら仕事を続けられます。また、家事や通院の付き添いがしやすくなる点や、通勤がないため体力を温存できる点も大きなメリットです。
【転職を検討する際のポイント】
転職を検討する際には、以下のポイントを考慮することが重要です。
- 勤務時間やシフトの柔軟性
- 介護と仕事の両立支援制度の有無
- 在宅勤務やリモートワークの導入状況
- 企業の理解とサポート体制
介護と仕事の両立が困難な場合でも、適切な仕事や職場を選ぶことで、両立を実現することができます。自分の状況に合わせて、最適な働き方を見つけることが重要です。
6 まとめ
介護と仕事の両立は決して容易ではありませんが、適切な支援制度や介護サービスを活用することで実現可能です。介護離職を避け、継続的に就業することは、経済的安定や社会とのつながりを維持する上で重要。両立支援制度や介護保険サービスの利用、ケアマネージャーへの相談、自身の時間確保など、様々なアプローチを組み合わせることで、より良いバランスを見出すことができます。
必要に応じて保険適用外サービスの利用や転職の検討も視野に入れ、柔軟に対応することが大切です。介護と仕事の両立を実現することで、キャリアを継続しながら大切な家族のケアを行うことができ、より充実した人生を送ることができるでしょう。